古事記現代語訳(40)朝鮮半島からの文化の渡来

朝鮮半島との活発な交流
応神天皇は、御子の大山守命に命じて、海部、山部、山守部(やまもりべ)、伊勢部を定めさせ、剣の池を造りました。

応神天皇の御代には、海の向こうから多くの人々が渡来しました。

建内宿禰はそれらの人々を率いて各地でため池を築かせ、田畑に水を引かせました。
その一つが「百済池(くだらのいけ)」と呼ばれる大きな池でした。

〇〇部とは、人民の集団に縁故のある名をつけて記念とし、まとめて支配します。
剣の池は、奈良県橿原市石川町にあるため池で、現在は「石川池」と呼ばれています。
 引用元:みくるの森
引用元:みくるの森百済池は、現在の奈良県北葛城郡広陵町にあったとされる大陸の灌漑技術を利用したため池。日本書紀には、韓人池(からひとのいけ)となっています。
また、百済の王・照古王は、牡馬一頭・牝馬一頭を阿知吉師という者に託して献上し、さらに大刀や大鏡も奉りました。

応神天皇は百済の王に対して、

「そちらに賢い者がいるならば、我が国に奉れ」
と仰せになりました。
すると百済の王は、和邇吉師(わにきし)という学者を遣わしました。
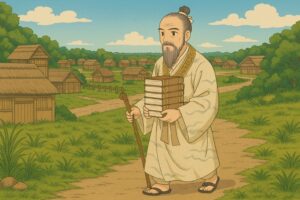
彼は論語十巻と・文字習得のための教材の千字文(せんじもん)一巻、合わせて十一巻を携えて献上し、日本に漢学を伝えました。
さらに、鍛冶職人の卓素、機織の西素(さいそ)、そしてお酒造りに秀でた仁番(にほ)、またの名を須須許理(すすこり)らも渡来しました。

応神天皇は仁番の造ったお酒を召し上がり、たいそうご機嫌になられて、

須須許理の醸した酒に酔ったぞ。和やかな酒、楽しき酒に心地よく酔ったぞ
とお歌いになりました。
そうして浮かれながら大坂への道を歩まれ、途中にあった大石をお杖でお打ちになると、不思議なことにその石がひとりでに逃げていきました。

それ以来、人々は「どんな堅い石でも、酔っ払いに出会えば逃げ出す」と言うようになったのです。
吉師は、朝鮮半島から渡来した官吏に与えられた尊称。
大坂への道は、二上山を越える道です。
古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)
文化の渡来
この御世に、海部、山部、山守部、伊勢部を定めたまひき。また劒の池を作りき。また新羅人まゐ渡り來つ。ここを以ちて建内の宿禰の命、引き率て、堤の池に渡りて、百濟の池を作りき。
- 海部、山部、山守部、伊勢部を定め(大山守命に命じたことをいう。人民の集団に縁故のある名をつけて記念とし、またこれを支配する。「何部を定めた」という記事が多い)
- 劒の池(奈良県高市郡)
- 堤の池に渡りて(不明瞭で諸説がある)
- 百濟の池(奈良県北葛城郡)
また百濟の國主照古王、牡馬壹疋、牝馬壹疋を、阿知吉師に付けて貢りき。この阿知吉師は阿直の史等が祖なり。また大刀と大鏡とを貢りき。また百濟の國に仰せたまひて、「もし賢し人あらば貢れ」とのりたまひき。かれ命を受けて貢れる人、名は和邇吉師、すなはち論語十卷、千字文一卷、并はせて十一卷を、この人に付けて貢りき。この和爾吉師は文の首等が祖なり。また手人韓鍛名は卓素、また呉服西素二人を貢りき。また秦の造の祖、漢の直の祖、また酒を釀むことを知れる人、名は仁番、またの名は須須許理等、まゐ渡り來つ。かれこの須須許理、大御酒を釀みて獻りき。ここに天皇、この獻れる大御酒にうらげて、御歌よみしたまひしく、
事無酒咲酒に、われ醉ひにけり。 (歌謠番號五〇)
- 百濟の國主照古王(百濟の第十三代の近肖古王)
- 阿知吉師(キシは尊称。下同じ。日本書紀には阿直支【あちき】)
- 千字文(広く行われている周興嗣次韵の千字文はまだ出来ていなかった)
- 手人韓鍛(工人である朝鮮の鍛冶人)
- 呉服西素(大陸風の織物工の西素という人)
- うらげて(浮かれ立って)
- 事無酒咲酒(事の無い愉快な酒。クシは酒)
- 大坂(二上山を越える道)















