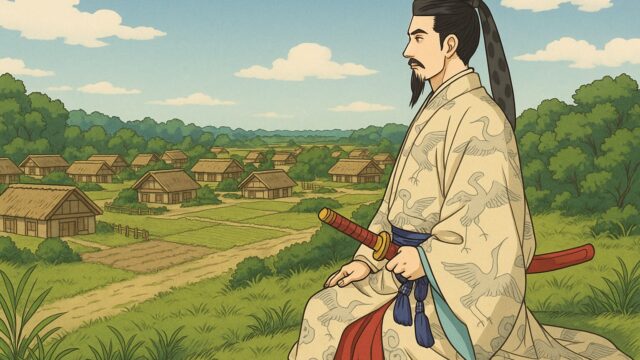古事記現代語訳(16)天孫降臨

邇邇芸命の天孫降臨
天照大御神と高木の神(高御産巣日神)は、乱れていた葦原中国(あしはらのなかつくに)が、建御雷神らの働きによって平定されたことを知ると、御子の天之忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)をお呼びになり、
「葦原中国はすっかり平らげられました。あなたは天降って、私が最初に命じた通り、あの国を治めなさい」

と仰せになりました。
忍穂耳命はその仰せに従い、すぐに天降る支度を整えましたが、そんなとき、お妃の万幡豊秋津師比売命(よろづはたとよあきつしひめのみこと)が男の御子をお生みになりました。

その子の名は天邇岐志国邇岐志天津日高日子番能邇邇芸命(あめにぎしくににぎしあまつひこひこほのににぎのみこと)、つまり、邇邇芸命です。
忍穂耳命は天照大御神に、
「私たち夫婦に世嗣が生まれました。この息子を地上に遣わすのがふさわしいかと存じます」
と言いました。

そこで天照大御神は、この孫の邇邇芸命が成長すると、改めてお傍に呼ばれ、

「葦原中国はおまえが治めるべき国です。私が命じる通りに天降りなさい」
と仰せになりました。
邇邇芸命は恭しく、「では、ただちに降りましょう」と答えて、支度を整えました。
邇邇芸命は、天照大御神が弟の須佐之男命との誓約(うけい)によって現れた子供の子供なので、「天照大御神の孫」ということになります。
やがて邇邇芸命が天降ろうとすると、四つ辻の真ん中にひとりの神が立ちはだかっていました。その神は上は高天原、下は葦原中国を照らすほど光り輝いていました。

天照大御神と高木の神はこれを見て天宇受売命(あめのうずめのみこと)を呼び、

「あなたは女性ですが、どんな荒ぶる神と向かい合っても物怖じしません。あの神に問いただしてください。私の孫の天降りを妨げているおまえは誰なのか、と」
と命じました。
天宇受売命が尋ねると、その神は答えました。

「私は国つ神の猿田毘古(さるたひこ)と申します。天孫がお降りになると聞き、道案内をしようと出迎えております」

この答えを聞き、天照大御神は安堵しました。
天照大御神は、天児屋命(あめのこやねのみこと)、布刀玉命(ふとだまのみこと)、天宇受売命、伊斯許理度売命(いしこりどめのみこと)、玉祖命(たまのおやのみこと)、この五柱を邇邇芸命の随伴としました。この五柱を五伴緒神(いつとものおのかみ)といいます。

さらに、八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)、八咫鏡(やたのかがみ)、草薙剣(くさなぎのつるぎ)の三種の神器を授けました。

「この鏡を私の魂だと思って祀りなさい。思金神は私の孫の政を助け仕えなさい」
と仰せになりました。

古事記はこのあたりから、伊勢が登場します。天照大御神が祀られている伊勢神宮の内宮は、「五十鈴の宮」と呼ばれています。内宮には、思金神と八咫鏡(やたのかがみ)も祀られています。
 引用元:flickr
引用元:flickr一方、伊勢神宮の外宮は、穀物の神である豊受の神をお祀りしています。豊受の神は、豊葦原の水穂の神霊でもあります。外宮の鎮座は、雄略天皇の御代であると伝わっています。
 引用元:flickr
引用元:flickrさらに、手力男神(たぢからおのかみ)、天石門別神(あめのいわとわけのかみ)らもお供に加えられました。
こうして邇邇芸命は、天の波士弓(はじゆみ)と天の真鹿児矢(まかごや)を持った天忍日命(あめのおしひのみこと)、天久米命(あまのくめのみこと)ら武勇の神々を先導に、多くの神々とともに雲を押し分け、天浮橋を渡って下界へと進みました。

ついに日向の高千穂の峰に天降り、串触岳(くしふるだけ)、さらに韓国岳(からくにだけ)を経て平地へと下り、やがて笠沙の岬に至りました。
 引用元:flickr
引用元:flickr日向の高千穂は、鹿児島県の霧島山の一峰、宮崎県西臼杵郡【にしうすきぐん】などの伝説地があります。
 引用元:flickr
引用元:flickr笠沙の岬は、鹿児島県薩摩半島の北西端にある野間岬の古称です。
 引用元:じゃらん
引用元:じゃらんそこで邇邇芸命は、
「ここは朝日も夕日も輝く、実に良い土地だ」

と喜ばれ、宮柱を高く立て、宮殿を営まれました。
そして、邇邇芸命は天宇受売命に命じました。

天宇受売命、猿田毘古神を伊勢まで送る
「私たちを導いてくれた猿田毘古神を伊勢まで送りなさい。そしてその功績を讃えて、彼の名を受け継いで仕えなさい」
こうして天宇受売命は猿田毘古神を伊勢まで送り届け、猿女の君(さるめのきみ)の祖となりました。

その後、猿田毘古神は伊勢の阿邪訶(あざか)に住み、漁の折に比良夫貝(ひらぶかい)に手を挟まれて溺れました。
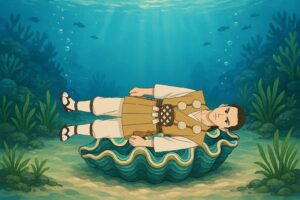
阿邪訶は、一志郡阿坂村で、現在は松阪市にあります。比良夫貝は、タイラギかシャコガイ、あるいは、月日貝だとされています。
海中に沈むときの猿田毘古神の名は底度久御魂(そこどくみたま)、泡が立つときは都夫多都御魂(つぶたつみたま)、水面で泡が開くときは阿和佐久御魂(あわさくみたま)と呼ばれています。
古事記には「溺れた」とはありますが「お隠れになった(亡くなった)」とは記されていません。
伝承によれば、猿田毘古神と猿女は邇邇芸命の祝福を受けて結ばれ、急いで周りにある荒木を集め、新居を建てたとされ、これが宮崎県高千穂の荒立神社の縁起だといわれています。
 引用元:flickr
引用元:flickr伊勢の猿田彦神社でも、猿田毘古神が邇邇芸命の御啓行(みちひらき)を務めたことから、道祖神として崇められています。そしてその境内には佐瑠女神社もあり、神前結婚式が行われています。

また、天宇受売命から猿女の君に名を替えたことから、結婚して名を替えた日本最初の女性だともされています。

海鼠の口の謎
天宇受売命は海に行き、魚たちを集め、「おまえたちは、我々天孫に仕えるか?」と問いました。

すべての魚が「はい」と答えましたが、海鼠(なまこ)だけは沈黙しました。

そこで宇受売命は「この口は返事ができない口なのね」と言って、小刀で海鼠の口を裂きました。ゆえに今も海鼠の口は裂けているのです。
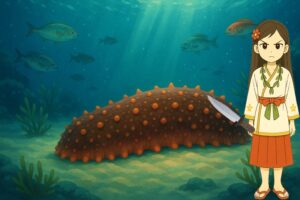
以来、志摩の国から魚類の貢ぎ物を奉る際には、猿女の君あてに贈られる慣わしとなりました。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)
六.邇邇藝の命
天降
ここに天照らす大御神高木の神の命もちて、太子正勝吾勝勝速日天の忍穗耳の命に詔りたまはく、「今葦原の中つ國を平け訖へぬと白す。かれ言よさし賜へるまにまに、降りまして知らしめせ」とのりたまひき。ここにその太子正勝吾勝勝速日天の忍穗耳の命答へ白さく、「僕は、降りなむ裝束せし間に、子生れましつ。名は天邇岐志國邇岐志天つ日高日子番の邇邇藝の命、この子を降すべし」とまをしたまひき。この御子は、高木の神の女萬幡豐秋津師比賣の命に娶ひて生みませる子、天の火明の命、次に日子番の邇邇藝の命二柱にます。ここを以ちて白したまふまにまに、日子番の邇邇藝の命に詔科せて、「この豐葦原の水穗の國は、汝の知らさむ國なりとことよさしたまふ。かれ命のまにまに天降りますべし」とのりたまひき。
ここに日子番の邇邇藝の命、天降りまさむとする時に、天の八衢に居て、上は高天の原を光らし下は葦原の中つ國を光らす神ここにあり。かれここに天照らす大御神高木の神の命もちて、天の宇受賣の神に詔りたまはく、「汝は手弱女人なれども、い向ふ神と面勝つ神なり。かれもはら汝往きて問はまくは、吾が御子の天降りまさむとする道に、誰そかくて居ると問へ」とのりたまひき。かれ問ひたまふ時に、答へ白さく、「僕は國つ神、名は猿田毘古の神なり。出で居る所以は、天つ神の御子天降りますと聞きしかば、御前に仕へまつらむとして、まゐ向ひ侍ふ」とまをしき。
- 天の八衢(天上のわかれ道)
- い向ふ神と面勝つ神なり(相対する神に顔で勝つ神だ)
ここに天の兒屋の命、布刀玉の命、天の宇受賣の命、伊斯許理度賣の命、玉の祖の命、并せて五伴の緒を支ち加へて、天降らしめたまひき。
- 五伴の緒(五つの部族。トモノヲは人々の団体。この五神以下の多くは皆天の岩戸の神話に出て、両者の密接な関係にあることを示す)
ここにその招ぎし八尺の勾璁、鏡、また草薙の劒、また常世の思金の神、手力男の神、天の石門別の神を副へ賜ひて詔りたまはくは、「これの鏡は、もはら我が御魂として、吾が御前を拜くがごと、齋きまつれ。次に思金の神は、前の事を取り持ちて、政まをしたまへ」とのりたまひき。
- ここにその招ぎし(岩戸の神話で天照らす大神を招いだ)
- 天の石門別の神(岩戸の神話における岩屋戸の神格)
- 政まをしたまへ(天皇の御前にあって政治をせよ。智恵思慮の神霊だからこのようにいう)
この二柱の神は、拆く釧五十鈴の宮に拜き祭る。次に登由宇氣の神、こは外つ宮の度相にます神なり。次に天の石戸別の神、またの名は櫛石窓の神といひ、またの名は豐石窓の神といふ。この神は御門の神なり。次に手力男の神は、佐那の縣にませり。
- 拆く釧五十鈴の宮(伊勢神宮の内宮。サククシロは、口のわれた腕輪の意で枕詞)
- 登由宇氣の神、こは外つ宮の度相にます神(伊勢神宮の外宮。トユウケの神は豊受の神とも書き、穀物の神。この神が従って下ったともなく、出たのは突然であるが、豊葦原の水穂の神霊だから出したのである。外宮の鎮座は、雄略天皇の時代の事と伝わる)
- 豐石窓の神(この二つの別名は、御門祭の祝詞に見える名で、門戸の神霊として尊んでいる)
かれその天の兒屋の命は、中臣の連等が祖。布刀玉の命は、忌部の首等が祖。天の宇受賣の命は猿女の君等が祖。伊斯許理度賣の命は、鏡作の連等が祖。玉の祖の命は、玉の祖の連等が祖なり。
かれここに天の日子番の邇邇藝の命、天の石位を離れ、天の八重多那雲を押し分けて、稜威の道別き道別きて、天の浮橋に、浮きじまり、そりたたして、竺紫の日向の高千穗の靈じふる峰に天降りましき。
- 天の八重多那雲を押し分けて、稜威の道別き道別きて(天から御座を離れ雲をおし分け威勢よく道を別けて)
- 天の浮橋に、浮きじまり、そりたたして(天の階段から下に浮渚があってそれにお立ちになったと解されている。古語を語り伝えたもの)
- 竺紫の日向の高千穗の靈じふる峰(鹿児島県の霧島山の一峰、宮崎県西臼杵郡【にしうすきぐん】など伝説地がある。思想的には大嘗祭の稲穂の上に下ったことである)
かれここに天の忍日の命天つ久米の命二人、天の石靫を取り負ひ、頭椎の大刀を取り佩き、天の波士弓を取り持ち、天の眞鹿兒矢を手挾み、御前に立ちて仕へまつりき。かれその天の忍日の命、こは大伴の連等が祖。天つ久米の命、こは久米の直等が祖なり。
- 天の石靫(堅固な靫【ゆぎ】。矢を入れて背負う)
- 頭椎の大刀(柄の頭がコブになつている大刀。実は石器だろう)
ここに詔りたまはく、「此地は韓國に向ひ笠紗の御前にま來通りて、朝日の直刺す國、夕日の日照る國なり。かれ此地ぞいと吉き地」と詔りたまひて、底つ石根に宮柱太しり、高天の原に氷椽高しりてましましき。
- 韓國に向ひ笠紗の御前にま來通りて(外国に向って笠紗の御前へ筋が通って。カササの御前は、鹿児島県川辺郡の岬。高千穂の嶽の所在をその方面にありとする伝えから来たのであろう)
猿女の君
かれここに天の宇受賣の命に詔りたまはく、「この御前に立ちて仕へまつれる猿田毘古の大神は、もはら顯し申せる汝送りまつれ。またその神の御名は、汝負ひて仕へまつれ」とのりたまひき。ここを以ちて猿女の君等、その猿田毘古の男神の名を負ひて、女を猿女の君と呼ぶ事これなり。かれその猿田毘古の神、阿耶訶に坐しし時に、漁して、比良夫貝にその手を咋ひ合はさえて海水に溺れたまひき。かれその底に沈み居たまふ時の名を、底どく御魂といひ、その海水のつぶたつ時の名を、つぶ立つ御魂といひ、その沫咲く時の名を、あわ咲く御魂といふ。
- 猿女の君(猿女の君は朝廷にあって神事その他に奉仕した)
- 阿耶訶(三重県一志郡【いちしぐん】)
- 比良夫貝(不明。月日貝だともいう)
- 底どく御魂(海底につく神霊)
ここに猿田毘古の神を送りて、還り到りて、すなはち悉に鰭の廣物、鰭の狹物を追ひ聚めて問ひて曰はく、「汝は天つ神の御子に仕へまつらむや」と問ふ時に、諸の魚どもみな「仕へまつらむ」とまをす中に、海鼠白さず。ここに天の宇受賣の命、海鼠に謂ひて、「この口や答へせぬ口」といひて、紐小刀以ちてその口を拆きき。かれ今に海鼠の口拆けたり。ここを以ちて、御世、島の速贄獻る時に、猿女の君等に給ふなり。
- 鰭の廣物、鰭の狹物(大小の魚)
- 島の速贄(志摩の国から奉る海産のたてまつり物)