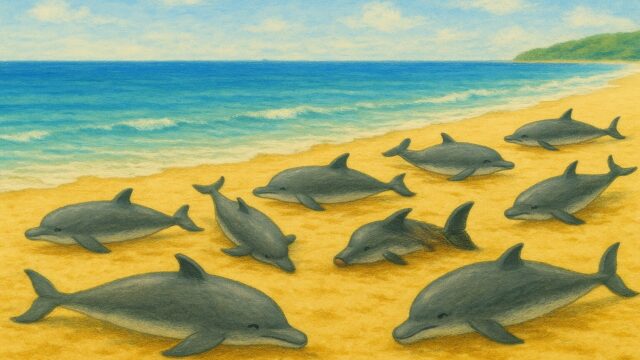古事記現代語訳(47)允恭天皇の氏姓制度改革

允恭天皇の誕生
男浅津間若子宿禰命(おあさづまわくごのすくねのみこと)は、反正天皇のお後を継がれるべき方でしたが、もともと長く病気に悩まれていたため、「この身体では帝位にはとても就けない」と固くご辞退なされました。
 参照元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「允恭天皇」
参照元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「允恭天皇」しかし、皇后の忍坂大中津比売命(おしさかのおおなかつひめのみこと)をはじめ臣下たちが熱心に勧めましたので、やむなく即位され、大和の遠飛鳥宮(とおあすかのみや)にお遷りになって、允恭(いんぎょう)天皇として、天下をお治めになりました。

遠飛鳥宮は、奈良県高市郡明日香村だとされています。
新羅から山のような貢物
その御代に、新羅の国主から八十一艘の船で山のような貢物が届けられました。

当時の朝鮮半島では、高句麗、新羅、百済の三国が三つ巴の争いを繰り広げていました。

新羅から大使として渡来したのは金波鎮漢紀武(こみぱちかにきむ)で、彼は医薬に通じていたため、長年の天皇のご病気を見事に癒やしました。

金波鎮漢紀武については、金は姓で、波鎮漢は官位、紀武は名前という説と、波鎮漢紀が官位で、武が名前という説があります。
盟神探湯による氏姓制度の改革
允恭天皇は、国内の多くの部族がめいめい勝手に氏姓(うじかばね)を名乗り出し、混乱しているのをいたく心配されるようになりました。

そこで大和の味白檮(うまかし)の地に、多くの災厄をもたらすとされている八十禍津日(やそまがつひ)の神を祀り、そこに「玖訶瓮(くかべ)」という大釜を据えて、煮えたぎる湯と泥を用いて「盟神探湯(くかたち)」の儀を行いました。

人々に自らの氏姓を名乗らせ、正直に本当の氏姓を述べた者は、鍋の中の泥を探っても無事でしたが、虚偽の申し立てをした者は、たちまちその手が焼けただれたということです。
允恭天皇はこうして氏姓を正しく定め、世の秩序を整えられました。

天皇は七十八歳で崩御され、御陵は河内の恵賀の長枝に営まれました。
氏(うじ)は、主に血縁を中心とした集団で、同じ祖先を持つという意識を持つ集団、姓(かばね)は、ヤマト王権が氏に対して与えた臣(おみ)や連(むらじ)などの称号です。
大和の味白檮は、奈良県高市郡明日香村豊浦の甘樫丘とされ、甘樫坐(あまかしにます)神社のあたりで、盟神探湯が行われたとされています。
 引用元:旅する明日香ネット
引用元:旅する明日香ネット5世紀後半に造営された大阪府藤井寺市の市ノ山古墳が、允恭天皇の河内の恵賀の長枝の御陵に治定され、仲哀天応の恵我長野西陵(えがのながののにしのみささぎ)や応神天皇の誉田御廟山古墳(こんだごびょうやまこふん)と同じ、古市古墳群の壮大な前方後円墳として伝わっています。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)
八十伴の緒の氏姓
天皇初め天つ日繼知らしめさむとせし時に、辭びまして、詔りたまひしく「我は長き病しあれば、日繼をえ知らさじ」と詔りたまひき。然れども大后より始めて、諸卿たち堅く奏すに因りて、天の下治らしめしき。この時、新羅の國主、御調物八十一艘獻りき。ここに御調の大使、名は金波鎭漢紀武といふ。この人藥の方を深く知れり。かれ天皇が御病を治めまつりき。
ここに天皇、天の下の氏氏名名の人どもの、氏姓が忤ひ過てることを愁へまして、味白檮の言八十禍津日の前に、玖訶瓮を据ゑて、天の下の八十伴の緒の氏姓を定めたまひき。また木梨の輕の太子の御名代として、輕部を定め、大后の御名代として、刑部を定め、大后の弟田井の中比賣の御名代として、河部を定めたまひき。
天皇御年七十八歳。(甲午の年正月十五日崩りたまひき。)御陵は河内の惠賀の長枝にあり。
- 大后(忍坂の大中津比賣)
- 金波鎭漢紀武(金が姓、武が名。波鎭漢紀は位置階級の称)
- 氏姓が忤ひ過て(ウヂは家の称号、カバネは家の階級であって朝廷から賜わるものである。家系を尊重した当時にあっては、これを社会組織の根本とした。しかるに長い間には、自然に誤る者もあり、故意に偽る者も出た)
- 味白檮の言八十禍津日の前(飛鳥の地で、マガツヒの神を祀ってある所。この神の威力により偽れる者に禍を与えようとする。)
- 玖訶瓮(湯を涌かしてその中の物を探らせる鍋)
- 天の下の八十伴の緒(多くの人々)
- 河内の惠賀の長枝(大阪府南河内郡)