古事記現代語訳(39)宮主矢河枝比売と髪長比売

応神天皇、葛野へ
応神天皇は成長され、軽島の明(あきら)の宮でご政務を執り行われるようになり、あるとき近江へとご巡幸になりました。

その途中で山城の宇治野にお立ちになりました。

そこで葛野(かずの)の方をご覧になると、実り豊かな良き土地が見えました。

軽島の明の宮は、現在の奈良県橿原市大軽町。春日神社の境内だとされています。
 引用元:みくるの森
引用元:みくるの森山城の宇治野は、現在の京都府宇治市。
葛野は、京都府葛野郡(かどのぐん)、戦後消滅しているので、現在は京都市です。
天皇はそこで感慨深く、こう歌われました。
「葉の茂った葛野を眺めると、幾千もの栄えた家々が立ち並び、国の中でも実に良き土地がここから見えるものだ」
宮主矢河枝比売との出会い
応神天皇は、そのまま木幡(こばた)の村にお進みになると、その道中で一人の美しい乙女に出会いました。

木幡は、現在の京都府宇治市の北部に位置する地名です。
天皇は乙女に、「あなたは誰の娘か?」とお尋ねになりました。
乙女は恭しく答えました。
「私は丸邇之比布礼能意富美(わにのひふれのおおみ)の娘、宮主矢河枝比売(みやぬしやがわえひめ)でございます」
丸邇氏は、奈良の春日の地で栄え、たびたびその娘を皇室に嫁がせています。
古事記の歌物語の多くが、この丸邇氏と関係があります。丸邇氏は、後に春日氏となりました。万葉集の柿本氏もこの流れです。
 参照元:柿本人麻呂(菊池容斎『前賢故実』)
参照元:柿本人麻呂(菊池容斎『前賢故実』)天皇は微笑みながら、「では明日、あなたの家に立ち寄ろう」と仰せられました。
矢河枝比売は急いで家に戻り、ことの次第を父に告げました。

父の意富美は大いに驚き、「その方は天皇陛下だぞ。何と畏れ多いことだ。失礼なきよう、心を尽くしてお仕え申しあげなさい」と諭しました。
家は隅々まで飾り整えられ、翌日、天皇をお迎えしました。

矢河枝比売が盃を捧げてご馳走でもてなすと、天皇は盃を取りながらお歌いになりました。

蟹の歌
「この蟹はどこの蟹か?遠く敦賀の蟹が横歩きをして、近江を超えてここまで来たものか?私もまた近江からきて、伊知遅島(いちぢしま)、美島(みしま)に着いたら、鳰鳥(かいつぶり)のように水に潜り、楽浪(ささなみ)へと向かう道を、どんどん真っ直ぐに進んだら、木幡の村でおまえに出会えた。おまえの後姿は盾のように凛として、歯並びは椎の実のように白く美しい。櫟井(いちい)の丸邇坂(わにざか)の土を眉墨にして、ちょうどよい色に色濃く描いた眉は、何とも麗しい。ああ、おまえは本当に美しい娘だね」

こうして天皇は矢河枝比売の美しさを深くお褒めになり、やがてお妃とされました。

当時、蟹は鹿とともに食材として親しまれていました。
伊知遅島や美島は、琵琶湖の島だと考えられますが、具体的な場所は不明です。

楽浪は、近江の西南部。
櫟井の丸邇坂は、奈良県天理市和爾町あたりとされています。和爾町のすぐ隣には、天理市櫟本(いちのもと)町という地名があり、天狗が住む巨大な櫟(イチイ)の木があったという伝説に由来しています。周辺には和爾下神社があります。

この矢河枝比売との間に生まれた御子が、宇遅能和紀郎子(うじのわきいらつこ)でした。

応神天皇には皇子十一人、皇女十五人がおられましたが、その中でも矢河枝比売が産んだ宇遅能和紀郎子を、ことのほか可愛がられました。
また、応神天皇は、日向の国の諸県君(もろかたのきみ)という豪族の娘で、髪長比売という非常に美しい乙女がいるとお聞きになり、宮中に召し仕えさせようと、はるばる呼び寄せられました。

髪長比売を皇子の大雀命に譲る応神天皇
皇子の大雀命(おおさざきのみこと)、のちの仁徳天皇は、髪長比売が船で難波の津に到着した時の姿をご覧になり、あまりの美しさに心を奪われてしまいました。
そこで、建内宿禰に、

「父上にお願いして、あの髪長比売を私の妃にしてもらえないだろうか」
と頼みました。
建内宿禰はすぐにその願いを応神天皇に伝えました。
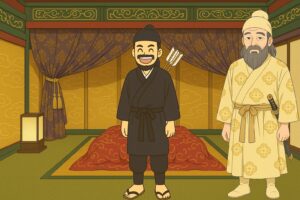
応神天皇はそれをお聞きになると、ある日の酒宴に大雀命を呼び寄せ、髪長比売にお酒を注がせ、その柏の葉の杯をそのまま大雀命に授けられました。

そして、にこやかに歌われました。
さぁ、皆のもの。野蒜を摘みに通る道端の橘の木、上の枝は鳥に荒らされ、下の枝は人にむしられてしまったが、中ほどの枝には花が咲き、ひっそりと三栗(みつぐり)のような実が隠れている。

そんな可憐で慎ましい乙女は、まさにお前にふさわしい。さあ、連れて行くがよい。
こうして天皇の許しを得た大雀命は、以前から噂に聞き、心に描いていた美しい乙女をついに妃とすることができました。

大雀命がその乙女にお詠みになった歌は、
遠い国の古波陀(こはだ)のお嬢さん、雷鳴(かみなり)のように音高く、噂には聞いていたが、ついに僕の妻になってくれたのだ。

遠い国の古波陀のお嬢さんが、素直に僕の妻になってくれた、本当にかわいいね。
大雀命は喜びの気持ちを歌に託して詠み、満ち足りた心で御前を下がって行きました。

古波陀は、髪長比売の故郷の日向、現在の宮崎県の地名だと思われます。
吉野の人たちの歌
吉野の人たちが、大雀命が身につけていた刀を見て、歌いました。

応神天皇の日の御子の大雀命
大雀命が持っている刀は鋭く
切っ先には不思議な霊力がある
その霊力は冬の木の根元に生える若芽のようです


吉野の人々は、地元の白樫を材料に臼を作って、その臼でお酒を造りました。そのお酒を朝廷に献上する際、口で太鼓の真似をして、身振り手振りで歌いました。

樫の樹で臼を作り、臼で醸造したお酒は、おいしいですよ
召し上がりください。私たちのお父さま
この歌は吉野の人たちが、朝廷に食べ物を献上するときは、今でも歌う歌です。
古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)
七.應神(応神)天皇
葛野(かずの)の歌
或る時天皇、近つ淡海の國に越え幸でましし時、宇遲野の上に御立して、葛野を望けまして、歌よみしたまひしく、
百千足る 家庭も見ゆ。
國の秀も見ゆ。 (歌謠番號四二)
- 近つ淡海の國(滋賀県)
- 宇遲野(京都府宇治郡)
- 葛野(京都市。今の桂川の平野)
- 千葉の(枕詞。葉の多い意で、葛に冠する)
- 百千足る 家庭も見ゆ(たくさん充実している村々も見える。ヤニハは、家屋のある平地)
- 國の秀も見ゆ(国土のすぐれている所も見える。クニノホは、「國のまほろば」の接頭語接尾語の無い形)
蟹の歌
百傳ふ 角鹿の蟹。
横さらふ 何處に到る。
伊知遲島 美島に著き、
鳰鳥の 潛き息衝き、
しなだゆふ 佐佐那美道を
すくすくと 吾が行ませばや、
木幡の道に 遇はしし孃子、
後方は 小楯ろかも。
齒並は 椎菱なす。
櫟井の 丸邇坂の土を、
初土は 膚赤らけみ
底土は に黒き故、
三栗の その中つ土を
頭著く 眞火には當てず
眉畫き 濃に書き垂れ
遇はしし女。
かもがと 吾が見し兒ら
かくもがと 吾が見し兒に
うたたけだに 向ひ居るかも
い副ひ居るかも。 (歌謠番號四三)
- 木幡の村(京都府乙訓郡)
- 丸邇の比布禮の意富美が女(丸邇氏は、奈良の春日に居住して富み栄え、しばしばその娘を皇室に納れている。古事記の歌物語の多くが、この氏と関係がある。後に春日氏となった。柿本氏もこの別れである。丸邇氏の歌物語については、角川源義君にその研究がある)
- 蟹や(ヤは提示の助詞。蟹は鹿と共に古代食膳の常用とされ親しまれていたので、これらに扮装して舞い歌われた。その歌は、そのものの立場において、歌うのでこれもその一つをもととしている)
- 百傳ふ(枕詞。多くの土地をつたい行く意という)
- 横さらふ(横あるきをして)
- 美島(いずれも所在不明)
- 鳰鳥の(枕詞。ニホドリノに同じ)
- しなだゆふ(枕詞。段になってたわんでいる意という)
- 後方は 小楯ろかも(うしろ姿は楯のようだ。ロは接尾語)
- 椎菱なす(椎のみや菱のようだ。諸説がある)
- 櫟井の(イチイの木の立つ井がある)
- 初土は(上の方の土)
- 三栗の(枕詞)
- 頭著く(頭にあたる)
- かもがと(かようにありたいと。現に今あるようにと。次のかくもがとも同じ)
- うたたけだに(語義不明。ウタタ(転)を含むとすれば、その副詞形で、転じて、今は変わっての意になる)
髪長比賣
蒜摘みに わが行く道の
香ぐはし 花橘は、
上枝は 鳥居枯らし、
下枝は 人取り枯らし、
三栗の 中つ枝の
ほつもり 赤ら孃子を、
いざささば 好らしな。 (歌謠番號四四)
堰杙打ちが 刺しける知らに、
蓴繰り 延へけく知らに、
吾が心しぞ いやをこにして 今ぞ悔しき。 (歌謠番號四五)
雷のごと 聞えしかども
相枕纏く。 (歌謠番號四六)
爭はず 寢しくをしぞも、
愛しみ思ふ。 (歌謠番號四七)
- 聞こしめしける日(酒宴をなされた日)
- 大御酒の柏を取らしめて(広い葉に酒を盛った)
- いざ子ども(さあ皆の者。子どもは目下の者をいう)
- ほつもり 赤ら孃子(語義不明。秀つ守りで、高く守っている意か。目立ってよい意に赤ら孃子を修飾するのだろう。日本書紀にはフホゴモリとある)
- いざささば(さあなされたら。ササは、動詞為の敬語の未然形だろう。動詞寝【ぬ】の敬語をナスという類)
- 水渟る(叙述による枕詞)
- 依網の池(大阪市東成区)
- 堰杙打ち(その池の水をたたえる井の杭を打ってあるのが)
- 刺しける知らに(ニは打消の助動詞ヌの連用形)
- 延へけく(のびていること。ケは時の助動詞キの古い活用形だろうとされる。以上比喩で、太子の思いがなされていたことをえがく)
- 道の後(遠い土地の)
- 古波陀孃子(コハダは日向の国の地名だろう)
- 寢しくをしぞも(寝たことを。上のシは時の助動詞。クはコトの意の助詞。ヲシゾモ、助詞)
国主歌(くずうた)
また、吉野の國主ども、大雀の命の佩かせる御刀を見て、歌ひて曰ひしく、
大雀 大雀。
佩かせる大刀、
本劍末ふゆ。
冬木の すからが下木の さやさや。 (歌謠番號四八)
横臼に 釀みし大御酒、
うまらに 聞こしもちをせ。
まろが父。 (歌謠番號四九)
- 吉野の國主(吉野山中の住民。國巣とも)
- 品陀の 日の御子(應神天皇の皇子樣)
- 本劍末ふゆ(剣の刃先が威力を現している)
- 冬木の すからが下木の(冬の木の枯れている木の下の。この二句、種々の説がある)
- さやさや(剣の清明であるのをたたえた語)
- 白檮の生(白樫の生えているところ)
- 横臼(たけの低い臼。その臼で材料をついて酒をかもす)
- 口鼓を撃ち(太鼓のような声を出して)
- 伎をなして(手ぶり物まねなどして)
- うまらに 聞こしもちをせ(うまそうに召しあがれ。ヲセは、食すの命令形)
- まろが父(われらが父よ)















