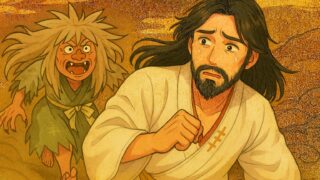古事記現代語訳(3)伊邪那岐命と伊邪那美命の「神生み」
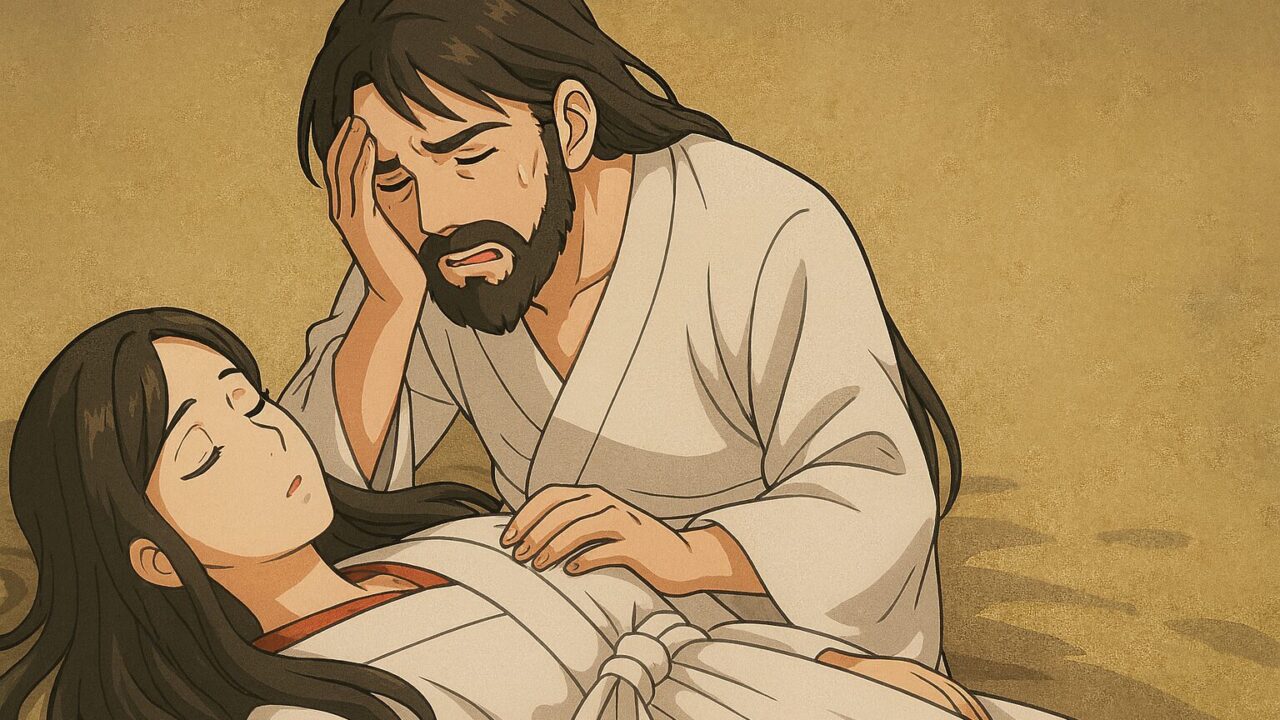
伊邪那岐命と伊邪那美命の神生み
伊邪那岐命・伊邪那美命のお二人は、島々を生み終えると、次は多くの神々をお生みになりました。

大事忍男神(おおごとおしをのかみ)をはじめとし、海の神の大綿津見神(おおわたつみのかみ)、河や水分の神々、風の神の志那都比古神(しなつひこのかみ)、木の神の久々能智神(くくのちのかみ)、山の神の大山津見神(おおやまつみのかみ)、野の神の野椎神(のづちのかみ)など、自然を司る神々が次々と誕生しました。

さらに、船の神の天鳥船(あめのとりふね)と、食べ物をつかさどる大宜都比売神(おおげつひめのかみ)、そして最後に火之迦具土神(ほのかぐつちのかみ)をお生みになりました。

静岡県浜松市の秋葉神社は、火の神、火之迦具土神を祀り、全国約400社の秋葉神社の総本宮です。防火や鎮火の神様とされています。
 引用元:ガッツレンタカー
引用元:ガッツレンタカー伊邪那美命の死
ところが、この火の神をお生みになったとき、伊邪那美命は大やけどをし、命を落とされてしまいました。

伊邪那岐命は、
「ああ、愛しい妻よ、たった一人の子のために、大事なお前を失ってしまうとは」と慟哭されました。
その涙は神と化し、その悲しみは天地に満ち溢れました。
伊邪那岐命の涙で出現した神は、香具山の麓の小高い場所の木の下においでになる泣澤女神(なきさわめのかみ)です。

香具山とは、現在の奈良県橿原市の天香久山(あまのかぐやま)のことをさします。標高は152メートル。南麓には天照大御神の岩戸隠れの伝承地とされる岩穴や、巨石をご神体とした天岩戸(あまのいわと)神社があり、山頂には国常立(くにとこたち)神社があります。
 引用元・橿原市公式
引用元・橿原市公式泣澤女神は、香具山の麓にあったとされる埴安の池の水神です。天香久山の北西麓の畝尾都多本神社(うねおつたもとじんじゃ)では、泣澤女神をお祀りしています。
 引用元:橿原市
引用元:橿原市伊邪那美命は、出雲の国と伯耆の国との境にある比婆之山に葬られました。比婆之山は、現在の広島県庄原市にある比婆山とされ、標高は1,299 mです。
 引用元:Dive! Hiroshima
引用元:Dive! Hiroshima悲嘆に暮れた伊邪那岐命は、怒りを込めて天之尾羽張(あめのおはばり)という名の十拳剣(とつかのつるぎ)を抜き、火之迦具土神を一太刀に斬り伏せられました。

十拳剣は、古事記に頻繁に登場しますが、「十掴みほどある長い剣」のことをさします。
火之迦具土神の血や身体からも新たな神々が生まれ出ましたが、それでもなお伊邪那岐命の悲しみは癒えません。
どうしても妻に再び会いたいと思った伊邪那岐命は、意を決して、死者の国、暗黒の黄泉(よみ)の国へと向かわれたのです。

黄泉の国は、地下にあるとされています。
古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)
神々の生成
既に國を生み竟へて、更に神を生みたまひき。かれ生みたまふ神の名は、大事忍男の神。次に石土毘古の神を生みたまひ、次に石巣比賣の神を生みたまひ、次に大戸日別の神を生みたまひ、次に天の吹男の神を生みたまひ、次に大屋毘古の神を生みたまひ、次に風木津別の忍男の神を生みたまひ、次に海の神名は大綿津見の神を生みたまひ、次に水戸の神名は速秋津日子の神、次に妹速秋津比賣の神を生みたまひき。(大事忍男の神より秋津比賣の神まで并はせて十神。)
- 大事忍男の神~大屋毘古の神(これらの神の系列は、家屋の成立を語るものと解せられる)
- 風木津別の忍男の神(風に対して堪えることを意味するらしい)
- 水戸の神(河口など、海に対する出入口の神)
この速秋津日子、速秋津比賣の二神、河海によりて持ち別けて生みたまふ神の名は、沫那藝の神。次に沫那美の神。次に頬那藝の神。次に頬那美の神。次に天の水分の神。次に國の水分の神。次に天の久比奢母智の神、次に國の久比奢母智の神。(沫那藝の神より國の久比奢母智の神まで并はせて八神。)
- 河海によりて持ち別けて生みたまふ神(海と河とで分担して生んだ神。以下水に関する神。アワナギ、アワナミは、動く水の男女の神、ツラナギ、ツラナミは、静水の男女の神。ミクマリは、水の配分。クヒザモチは水を汲む道具。)
次に風の神名は志那都比古の神を生みたまひ、次に木の神名は久久能智の神を生みたまひ、次に山の神名は大山津見の神を生みたまひ、次に野の神名は鹿屋野比賣の神を生みたまひき。またの名は野椎の神といふ。(志那都比古の神より野椎まで并はせて四神。)
- 志那都比古の神(息の長い男の義)
- 久久能智の神(木の間を潜る男の義)
この大山津見の神、野椎の神の二神、山野によりて持ち別けて生みたまふ神の名は、天の狹土の神。次に國の狹土の神。次に天の狹霧の神。次に國の狹霧の神。次に天の闇戸の神。次に國の闇戸の神。次に大戸或子の神。次に大戸或女の神。(天の狹土の神より大戸或女の神まで并はせて八神。)
- 天の狹土の神~大戸或女の神(山の神と野の神とが生んだ諸神の系列は、山野に霧がかかって迷うことを表現する)
次に生みたまふ神の名は、鳥の石楠船の神、またの名は天の鳥船といふ。次に大宜都比賣の神を生みたまひ、次に火の夜藝速男の神を生みたまひき。またの名は火の炫毘古の神といひ、またの名は火の迦具土の神といふ。この子を生みたまひしによりて、御陰やかえて病み臥せり。たぐりに生りませる神の名は金山毘古の神。次に金山毘賣の神。次に屎に成りませる神の名は、波邇夜須毘古の神。次に波邇夜須毘賣の神。次に尿に成りませる神の名は彌都波能賣の神。次に和久産巣日の神。この神の子は豐宇氣毘賣の神といふ。かれ伊耶那美の神は、火の神を生みたまひしに因りて、遂に神避りたまひき。(天の鳥船より豐宇氣毘賣の神まで并はせて八神。)およそ伊耶那岐伊耶那美の二神、共に生みたまふ島壹拾四島、神參拾五神。(こは伊耶那美の神、いまだ神避りまさざりし前に生みたまひき。ただ意能碁呂島は生みたまへるにあらず、また蛭子と淡島とは子の例に入らず。)
- 鳥の石楠船の神(鳥の如く早く軽く行くところの、石のように堅いクスノキの船)
- 大宜都比賣の神(穀物の神。この神に関する神話が「須佐の男の神」の「穀物の種」]にある)
- たぐり(吐瀉物。以下排泄物によって生まれた神は、火を防ぐ力のある神である)
- 波邇夜須毘古の神・波邇夜須毘賣の神(埴土の男女の神)
- 彌都波能賣の神(水の神)
- 和久産巣日の神(若い生産力の神)
- 豐宇氣毘賣の神(これも穀物の神。以上の神の系列は、野を焼いて耕作する生活を語る)
- 神參拾五神(実数四十神だが、男女一対の神を一として数えれば三十五になる)
黄泉の国
かれここに伊耶那岐の命の詔りたまはく、「愛しき我が汝妹の命を、子の一木に易へつるかも」とのりたまひて、御枕方に匍匐ひ御足方に匍匐ひて、哭きたまふ時に、御涙に成りませる神は、香山の畝尾の木のもとにます、名は泣澤女の神。かれその神避りたまひし伊耶那美の神は、出雲の國と伯伎の國との堺なる比婆の山に葬めまつりき。ここに伊耶那岐の命、御佩の十拳の劒を拔きて、その子迦具土の神の頸を斬りたまひき。ここにその御刀の前に著ける血、湯津石村に走りつきて成りませる神の名は、石拆の神。次に根拆の神。次に石筒の男の神。次に御刀の本に著ける血も、湯津石村に走りつきて成りませる神の名は、甕速日の神。次に樋速日の神。次に建御雷の男の神。またの名は建布都の神、またの名は豐布都の神三神。次に御刀の手上に集まる血、手俣より漏き出て成りませる神の名は、闇淤加美の神。次に闇御津羽の神。(上の件、石拆の神より下、闇御津羽の神より前、并はせて八神は、御刀に因りて生りませる神なり。)
- 香山(奈良県磯城郡の天の香具山。神話に実在の地名が出る場合は、大抵その神話の伝えられている地方を語る)
- 畝尾(うねりのある地形の高み)
- 泣澤女の神(香具山の麓にあった埴安の池の水神。泣澤の森そのものを神体としている)
- 比婆の山(広島県比婆郡に伝説地がある)
- 十拳の劒(十つかみある長い剣)
- 湯津石村(神聖な岩石。以下神の系列によつて鉄鉱を火力で処理して刀剣を得ることを語る。イハサクの神からイハヅツノヲの神まで岩石の神霊。ミカハヤビ、ヒハヤビは火力。タケミカヅチノヲは剣の威力。クラオカミ、クラミツハは水の神霊。クラは渓谷。御刀の手上は、剣のつか。タケミカヅチノヲは「天照らす大御神と大国主の神」の「国譲り」、「神武天皇」の「熊野より大和へ」に神話がある)
殺さえたまひし迦具土の神の頭に成りませる神の名は、正鹿山津見の神。次に胸に成りませる神の名は、淤縢山津見の神。次に腹に成りませる神の名は、奧山津見の神。次に陰に成りませる神の名は、闇山津見の神。次に左の手に成りませる神の名は、志藝山津見の神。次に右の手に成りませる神の名は、羽山津美の神。次に左の足に成りませる神の名は、原山津見の神。次に右の足に成りませる神の名は、戸山津見の神。(正鹿山津見の神より戸山津見の神まで并はせて八神。)かれ斬りたまへる刀の名は、天の尾羽張といひ、またの名は伊都の尾羽張といふ。
- 正鹿山津見の神~戸山津見の神(各種の山の神)
- 天の尾羽張・伊都の尾羽張(幅の広い剣の義。水の神と解せられ、「天照らす大御神と大国主の神」の「国譲り」]に神話がある。別名のイツは、威力の意。)
ここにその妹伊耶那美の命を相見まくおもほして、黄泉國に追ひ往でましき。
- 黄泉國(地下にありとされる空想上の世界。黄泉の文字は漢文から来る)