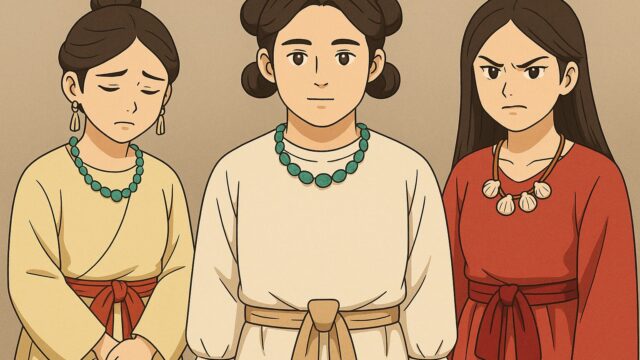古事記現代語訳(36)応神天皇の誕生

建内宿禰の夢に気比大神登場
品陀和気命(ほむだわけのみこと)、第十五代・応神天皇は、大和の軽島豊明宮(かるしまのとよあきらのみや)で、天下をお治めになりました。

神功皇后が大和に凱旋された後、建内宿禰はまだ幼い天皇をお連れして、まずは戦の穢れを祓うために近江や若狭を巡り、越前の鹿角(つぬが)の地に仮宮を建ててお住まいになりました。

そんなとき、土地の神である伊奢沙和気大神(いささわけのおおかみ)が建内宿禰の夜の夢に現れ、こう告げました。

「私の名を、この御子のお名前と取り替えていただきたい」
宿禰は恐れ入り、「ありがたくお受け致します」と答えました。すると大神は続けて仰せられました。
「明日の朝、浜辺に参られよ。名前を替えた証に贈り物を献じよう」
翌朝、宿禰が応神天皇をお連れして浜に出ると、鼻の先が潰れた多くのイルカが打ち上げられていました。

これを見て宿禰は、社に使いを立てて、「御饌のお魚をどっさり賜り、ありがとうございます」と感謝を申し上げました。

その時より、この神を「御食津大神(みけつおおかみ)」と称え、今は「気比大神」と呼んでいます。
また、イルカの鼻から流れた血が浦を染めたので、鹿角(つぬが)を「血浦」と呼ぶようになり、後に「敦賀」と称するようになりました。

大和の軽島豊明宮は、現在の奈良県橿原市大軽町にあったとされています。大軽春日神社の境内には、伝承碑と飛鳥時代に創建されたと伝わる軽寺跡があります。

福岡県敦賀市の気比神宮には、この伊奢沙和気大神を主祭神に、仲哀天皇と神功皇后も祀っています。

やがて応神天皇は母上の待つ大和へお還りになりました。神功皇后は歓喜され、さっそくお酒を醸して息子である天皇に献じながら、次の歌をお詠みになりました。

「このお酒は、私が醸したものではございません。常世国におられる久志能加美、御神酒の神の少名毘古那神が、御子の強運を祝って、喜び舞いながら造られた神酒でございます。さあ、盃を乾かさず召し上がってくださいませ」


これに対して、建内宿禰が応神天皇のために歌われました。
「このお酒を醸した人は、臼を太鼓に見立てて、歌いながら舞いながら造ったせいか、じっくり味わえば自然に歌いたく舞いたくなる、不思議に楽しいお酒でございます」

これは「酒楽(さけくら)の歌」と呼ばれ、御代を寿ぐ祝いの歌となりました。
このようにして応神天皇は、母・神功皇后の大いなる功績を継ぎ、天下をお治めになるに至ったのです。

神功皇后様は百歳で崩御されました。狹城(さき)の楯列(たたなみ)の御陵にお葬り申し上げました。

少名毘古那神は、大国主命の相棒として、国造りをした小柄な神様で、国造りが完了する前に、突然、常世国に行ってしまったとされています。

狹城の楯列の御陵、別名、狭城盾列池上陵(さきのたたなみのいけのえのみささぎ)は、五社神古墳(ごさしこふん)とも呼ばれ、奈良市山陵町にあります。全長267メートルの前方後円墳です。
古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)
気比の大神
かれ建内の宿禰の命、その太子を率まつりて、御禊せむとして、淡海また若狹の國を經歴りたまふ時に、高志の前の角鹿に、假宮を造りてませまつりき。ここに其地にます伊奢沙和氣の大神の命、夜の夢に見えて、「吾が名を御子の御名に易へまくほし」とのりたまひき。ここに言祷ぎて白さく、「恐し、命のまにまに、易へまつらむ」とまをす。またその神詔りたまはく、「明日の旦濱にいでますべし。易名の幣獻らむ」とのりたまふ。かれその旦濱にいでます時に、鼻毀れたる入鹿魚、既に一浦に依れり。ここに御子、神に白さしめたまはく、「我に御食の魚給へり」とまをしたまひき。かれまたその御名をたたへて御食津大神とまをす。かれ今に氣比の大神とまをす。またその入鹿魚の鼻の血臭かりき。かれその浦に名づけて血浦といふ。今は都奴賀といふなり。
- 御禊(水によって穢を祓う行事)
- 角鹿(越前の国の敦賀市)
- 伊奢沙和氣の大神の命(敦賀市気比神宮の祭神)
- 易名の幣(名を取り替えた印の贈り物)
酒楽(さけらく)の歌曲
ここに還り上ります時に、その御祖息長帶日賣の命、待酒を釀みて獻りき。ここにその御祖、御歌よみしたまひしく、
酒の長 常世にいます
石立たす 少名御神の、
神壽き 壽き狂ほし
豐壽き 壽きもとほし
獻り來し 御酒ぞ
乾さずをせ。ささ。 (歌謠番號四〇)
その鼓 臼に立てて
歌ひつつ 釀みけれかも、
舞ひつつ 釀みけれかも、
この御酒の 御酒の
あやに うた樂し。ささ。 (歌謠番號四一)
- 待酒(人を待って飲む酒)
- 酒の長(酒を司る長官。原文【久志能加美】美はミの甲類の字であり、神のミは乙類であるから、酒の神とする説は誤り)
- 常世(永久の世界。また海外。スクナビコナは海外へ渡ったという)
- 石立たす(石のように立っておいでになる)
- 少名御神(スクナビコナに同じ)
- 豐壽き 壽きもとほし(祝い言をさまざまにして)
- 乾さずをせ(盃が乾かないように続けて召し上がれ)
- ささ(はやし詞)
- 鼓(後世のツヅミの大きいもの。太鼓)
- 臼に立てて(酒を醸す入れ物として)
- 釀みけれかも(酒を作ったからか。疑問の已然条件法)
- うた樂し(大変にたのしい)
- 酒樂(歌曲の名。この二首、琴歌譜【きんかふ】にもある)
- 惠賀の長江(大阪府南河内郡)
- 狹城の楯列の陵(奈良県生駒郡)