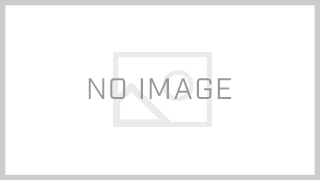古事記現代語訳(30)倭建命②西征

大碓命の死
ある日、景行天皇は御子の小碓命(おうすのみこと)、のちの倭建命に向かって、
「おまえの兄は、どうしてこの頃、朝夕の食事に顔を出さないのだ。おまえが行って、よく諭してまいれ」
とお命じになりました。

大碓命と小碓命は双子の兄弟でした。『日本書紀』によると、二人が双子だったため、父親の景行天皇がいぶかしく思い、臼に向かって叫んだため、このような名前で呼ばれるようになったそうです。

しかし五日経っても大碓命は顔を見せません。天皇が改めてお尋ねになると、小碓命は平然として、
「もう諭しましたよ」と答えました。
「では、どのように諭したのか?」

「朝早く厠に入ったところを待ち伏せして捕らえ、手足を折って薦に包んで捨てました」と、何事もなかったかのように話したのです。

景行天皇は、小碓命の荒々しい性格を恐ろしく思い、彼をそばから遠ざけようと考えました。

熊曽建兄弟の討伐
そこで小碓命にお命じになったのが、西の方の従わぬ熊曽建兄弟の討伐でした。

小碓命は伊勢に赴き、叔母の倭比売命に別れを告げました。

熊曽建については、クマソは地名で、クマの地【熊本県】とソの地【鹿児島県】とを合わせたものです。タケルは勇者の意味。兄弟は二人となっています。

倭比売命は、天照大御神に仕える斎宮でした。伊勢には、伊勢神宮の別宮として、倭姫宮(やまとひめのみや)があり、女性の守護や道開きの神として信仰されています。
 引用元:伊勢神宮
引用元:伊勢神宮倭比売命は、景行天皇の妹にあたる女性です。
倭比売命は甥の小碓命を心配して、上着と袴、そして懐剣を授けてくださいました。

その頃、小碓命はまだ少年で、髪を額で結っておられました。
小碓命はそれから、今の日向、大隅、薩摩の地方へと向いました。

やがて熊曽建の館に近づくと、館の周囲には三重に軍勢が取り囲んで守っていました。
ちょうど新築祝いの宴を催すところのようで、大騒ぎで準備していました。
宴の日、小碓命は結った髪をほどき、叔母からもらった衣装を身にまとって乙女に姿を変え、女たちに交じって館に入りました。
 引用元:ヤマトタケル(菊池容斎画)
引用元:ヤマトタケル(菊池容斎画)
 引用元:女装するヤマトタケル(月岡芳年画)
引用元:女装するヤマトタケル(月岡芳年画)
熊曽建の兄弟は、その美しさに心を奪われ、間に座らせて大喜びし、宴は大いに盛り上がりました。

やがて宴が最高潮に達した時、小碓命は懐から剣を抜き、兄の熊曽建の襟首をつかんで胸を突き刺しました。

弟の建は驚いて逃げ出しましたが、小碓命はすぐに追いかけ、階段下で肩を掴み、剣で突き刺しました。

建はもはや逃げられぬと悟り、
「その刀はしばらく動かさないでください。いったいあなたはどなたですか?」と尋ねました。
小碓命は答えました。
「俺は、この大八島国を治める大帯日子淤斯呂和気天皇(おおたらしひこおしろわけのすめらみこと)の御子、倭男具那王(やまとをぐなのおう)だ。大和の日代の宮にいた。天皇の勅命により、お前たちを討ちに来たのだ」
弟の建はこれを聞いて感服し、
「西の国には私たち以上の強者はおりません。しかし大和には、私たちを超える勇士がおられたのですね。ならばあなたに私たちの名を献じましょう。これからあなたは『倭建命(やまとたけるのみこと)』と名乗られるがよいでしょう」と言い残しました。
小碓命はそのまま熊曾建を熟した瓜のように斬り裂き、以来「倭建命」と名乗るるようになったのです。
『日本書紀』では、「日本武尊」という漢字があてられています。
出雲建を退治
倭建命は帰途、山の神、川の神、海峡の神らをことごとく平定し、さらに出雲に赴きました。そこで出雲建という荒くれ者を退治しました。

倭建命はまず赤檮(いちい)の木で木剣を作りました。それから、出雲建に親しみを装って近づき、肥の河で一緒に水浴びをしました。

そして、先に河から上がって出雲建の太刀を、偽の木剣と取り換えたのです。
そこで「さあ、試合をしようか」と声をかけ、両者が刀を抜こうとしましたが、出雲建の刀は木剣で抜けません。倭建命はすかさず本物の太刀を抜き、出雲建を斬り伏せました。

その時に詠まれた歌、
雲のむら立つ出雲の建が腰にした大刀は、蔓を巻きすぎて刃も抜けず、なんと哀れなことよなぁ。
こうして西の国から出雲に至るまで賊を平らげ、倭建命は都へ凱旋し、景行天皇にことの次第をすべて奏上しました。

『日本書紀』では、「日本武尊」は熊襲征伐の帰路に、吉備と難波には立ち寄っていますが、出雲には立ち寄ってはいません。

『日本書紀』では、飯入根(いいいりね)が、兄の出雲振根(いずものふるね)の留守中に、「出雲大神の宮」に収めてあった「天夷鳥(あめのひなどり)が天から持って来たと伝わる神宝(かむたから)」を崇神天皇の使者である武諸隅(たけもろすみ)に献上してしまい、
振根が立腹し、弟の入根を殺害するというエピソードがあります。その殺害方法が、倭建命が出雲建を殺害した手口とほぼ同じです。
殺された入根の弟の甘美韓日狭(うましからひさ)と息子の鸕濡渟(うかずくぬ)は、この事実を朝廷に報告したため、振根は、天皇の遣わした吉備津彦(きびつひこ)と武渟川別(たけぬなかわけ)によって誅殺されてしまいます。
南九州には、本州とは異なる文化を持つ「熊曽」や「隼人」という集団がいました。
ヤマト政権は、彼らを支配下に置くために、何度も遠征しています。
鹿児島県霧島市隼人町には、隼人族の霊魂を供養する隼人塚があります。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)
倭建の命の西征
天皇、小碓の命に詔りたまはく、「何とかも汝の兄、朝夕の大御食にまゐ出來ざる。もはら汝ねぎ教へ覺せ」と詔りたまひき。かく詔りたまひて後、五日に至るまでに、なほまゐ出でず。ここに天皇、小碓の命に問ひたまはく、「何ぞ汝の兄久しくまゐ出來ざる。もしいまだ誨へずありや」と問ひたまひしかば、答へて白さく、「既にねぎつ」とまをしたまひき。また「いかにかねぎつる」と詔りたまひしかば、答へて白さく、「朝署に厠に入りし時、待ち捕へ搤み批ぎて、その枝を引き闕きて、薦につつみて投げ棄てつ」とまをしたまひき。
- ねぎ(なだめ乞う)
- いかにかねぎつる(どんなふうになだめ乞うたのか)
- 朝署(朝早く)
- その枝(手足)
ここに天皇、その御子の建く荒き情を惶みて、詔りたまひしく、「西の方に熊曾建二人あり。これ伏はず、禮旡き人どもなり。かれその人どもを取れ」とのりたまひて、遣したまひき。この時に當りて、その御髮を額に結はせり。ここに小碓の命、その姨倭比賣の命の御衣御裳を給はり、劒を御懷に納れていでましき。かれ熊曾建が家に到りて見たまへば、その家の邊に、軍三重に圍み、室を作りて居たり。ここに御室樂せむと言ひ動みて、食物を設け備へたり。かれその傍を遊行きて、その樂する日を待ちたまひき。ここにその樂の日になりて、童女の髮のごとその結はせる髮を梳り垂れ、その姨の御衣御裳を服して、既に童女の姿になりて、女人の中に交り立ちて、その室内に入ります。ここに熊曾建兄弟二人、その孃子を見感でて、おのが中に坐せて、盛に樂げつ。かれその酣なる時になりて、御懷より劒を出だし、熊曾が衣の矜[#「矜」はママ]を取りて、劒もちてその胸より刺し通したまふ時に、その弟建見畏みて逃げ出でき。すなはちその室の椅の本に追ひ至りて、背の皮を取り劒を尻より刺し通したまひき。ここにその熊曾建白して曰さく、「その刀をな動かしたまひそ。僕白すべきことあり」とまをす。ここに暫許して押し伏せつ。ここに白して言さく、「汝が命は誰そ」と白ししかば、「吾は纏向の日代の宮にましまして、大八島國知らしめす、大帶日子淤斯呂和氣の天皇の御子、名は倭男具那の王なり。おれ熊曾建二人、伏はず、禮なしと聞こしめして、おれを取り殺れと詔りたまひて、遣せり」とのりたまひき。ここにその熊曾建白さく、「信に然らむ。西の方に吾二人を除きては、建く強き人無し。然れども大倭の國に、吾二人にまして建き男は坐しけり。ここを以ちて吾、御名を獻らむ。今よ後、倭建の御子と稱へまをさむ」とまをしき。この事白し訖へつれば、すなはち熟苽のごと、振り拆きて殺したまひき。かれその時より御名を稱へて、倭建の命とまをす。然ありて還り上ります時に、山の神河の神また穴戸の神をみな言向け和してまゐ上りたまひき。
- 熊曾建二人(クマソは地名で、クマの地【熊本県】とソの地【鹿児島県】とを合わせ称する。タケルは勇者の義。物語では兄弟二人となっている)
- 御髮を額に結はせり(男子少年の風俗)
- その姨倭比賣の命(父の妹に当たる)
- 御室樂(新築を祝う酒宴)
- 衣の矜(衣服の襟)
- 室の椅(庭上におりる階段)
- 今よ後(今から後。ヨは助詞。ユ、ヨリに同じ)
- 倭建の御子(日本書紀には、日本武尊【やまとたけるのみこと】と書く)
- 熟苽のごと(熟した瓜のように)
- 穴戸の神(海峡の神)
- 言向け和して(平定しおだやかにして)
出雲建
すなはち出雲の國に入りまして、その出雲の國の建を殺らむとおもほして、到りまして、すなはち結交したまひき。かれ竊に赤檮もちて、詐刀を作りて、御佩しとして、共に肥の河に沐しき。ここに倭建の命、河よりまづ上りまして、出雲建が解き置ける横刀を取り佩かして、「易刀せむ」と詔りたまひき。かれ後に出雲建河より上りて、倭建の命の詐刀を佩きき。ここに倭建の命「いざ刀合はせむ」と誂へたまふ。かれおのもおのもその刀を拔く時に、出雲建、詐刀をえ拔かず、すなはち倭建の命、その刀を拔きて、出雲建を打ち殺したまひき。ここに御歌よみしたまひしく、
黒葛多纏き さ身無しにあはれ。 (歌謠番號二四)
かれかく撥ひ治めて、まゐ上りて、覆奏まをしたまひき。
- すなはち出雲の國に入りまして(この物語は日本書紀には、出雲振根がその弟飯入根を殺した話になっている)
- 詐刀(にせの刀。木刀)
- やつめさす(枕詞。八雲立つの転訛。日本書紀にはヤクモタツになっている)
- 黒葛多纏き(柄や鞘に植物の蔓をたくさん巻いてある)
- さ身無しにあはれ(刀身が無いことだ。アハレは感動を表示している)