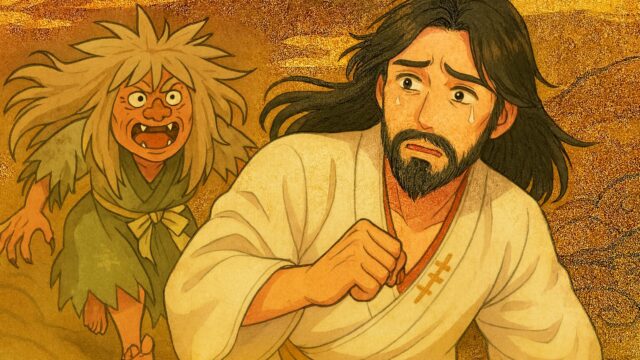古事記現代語訳(12)「大国主命(八千矛神)と越の国の沼河比売の恋
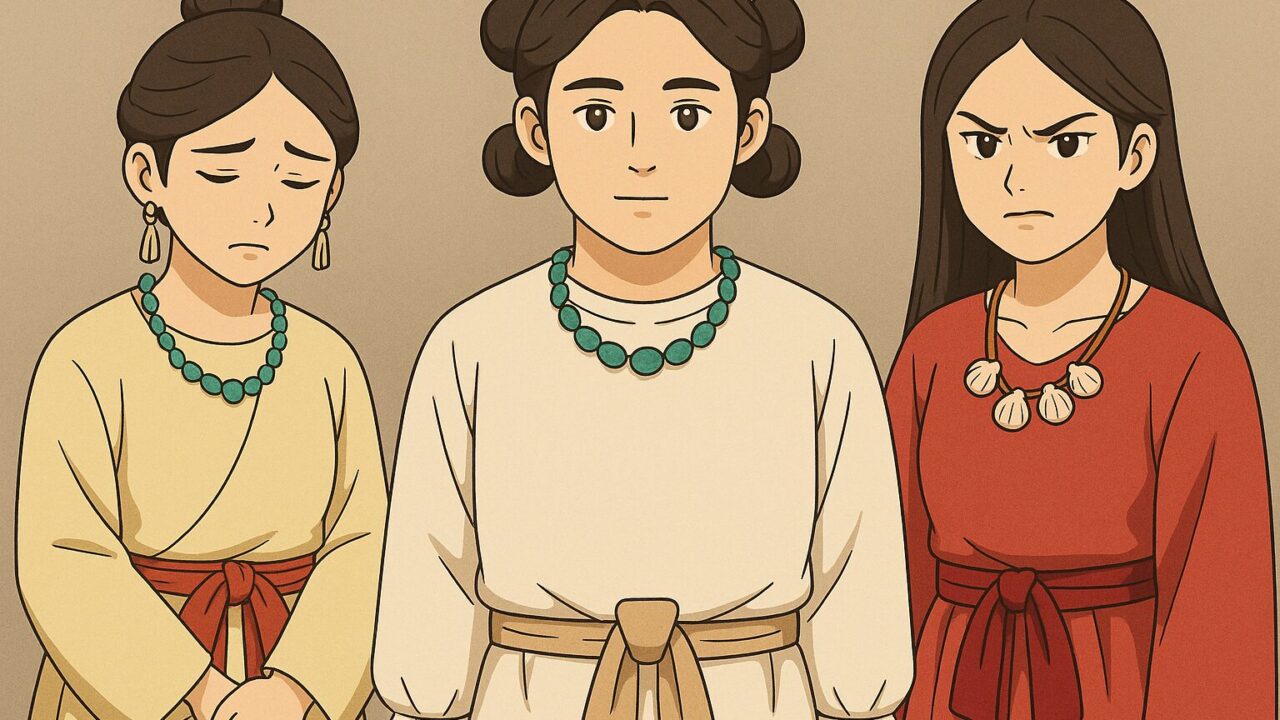
沼河比売との恋
大国主命、八千矛神(やちほこのかみ)が、沼河比売(ぬなかわひめ)と結婚しようと越の国、現在の新潟あたりまで行きました。
その時に詠まれた歌は、

八千矛神とは、多くの武器を持つ神という意味です。
当時の婚姻は、夜間に男性が女性の家を訪れる形態でした。

遠い越の国に、賢くて美しい娘がいると聞いた。私は方々で妻を探し求めてきたが、やっと見つけたぞ。
刀の緒も解かず、羽織も脱がずに、こうしてあなたの家の戸の前に立っている。眠っている娘よ、どうか出てきてはくれないか。
青い山ではトラツグミや雉たちが鳴いている。庭先では鶏も鳴いている。腹立たしいほどに騒がしい。いっそやっつけてしまいたいくらいだ。
といった内容でした。
沼河比売は、戸を開けず家の中から、

八千矛神さま、私はしおれた草のような女ですが、心は水鳥のように漂っています。
今は拒んでいても、やがてあなたのものになるでしょう。どうかその時まで長生きしてください。

と歌いました。さらに、

青い山に日が隠れたら、暗い夜になるでしょう。あなたはその時、明るい朝のような笑顔で訪ねてきてください。
手を取り合い、一緒に過ごしましょう。
あなたは 足を伸ばしてゆっくりお休みください。
八千矛神さま、そんなにがっかりなさらないでください。
そして、
次の日の夜が来て、二人はついに結ばれました。
北越、福井から新潟あたりの沼河の地に住む姫という意味。ヌナカハは今の新潟県糸魚川市(いといがわし)だとされています。

大国主命を引き留めることに成功した須勢理比売
ある日、大国主命は正妻の須勢理比売の嫉妬を疎ましく思い、出雲を出て大和へ向かおうとされました。
そこで、片手を馬の鞍にかけ、片足を鐙に入れながら、歌いました。

漆黒の黒い衣も カワセミ色の青い衣も おまえには似合わない。だけど、茜草で染めた衣なら、おまえにぴったりだ。
愛しい妻よ、
大空を飛ぶ鳥のように 私が自由気ままに振舞えば、お前は泣かないと言っても、
山肌に立つ 一本の薄のようにうなだれ 涙を流すだろう。
そして朝の雨の霧の中に立つだろう。ああ、若草のような私の妻よ。

その歌に応えて、須勢理比売が杯を捧げました。
八千矛神さま、私の夫、大国主さま。あなたは男ですから、岬ごとに若草のような妻を持たれているのでしょう。けれど私は女。あなた以外に男性はなく、夫もいません。玉のような白い腕であなたを抱き、淡雪のような胸であなたを受け止めましょう。さぁ、足をのばしてお休みください。美味しいお酒を召し上がり、一緒に眠りましょう。
こうして二人は再び杯を交わし、今日まで夫婦として鎮まっていると伝えられています。
大国主命の妻は、正妻の須勢理比売と因幡の白兎伝説の八上比売、越の国の沼河比売の3人のほかにも、「宗像三女神」の一柱である多紀理毘売命、多岐都比売命と同一神だと思われる神屋楯比売(かむやたてひめ)、さらに鳥耳神(とりみみのかみ)等がいます。
しかし、須勢理比売たち3名以外には、具体的な逸話は残されていません。大国主命には、妻の数合計11人、子供の数は『古事記』には180人、『日本書紀』には181人とされています。

1665年、出雲大社から徒歩5分に位置する命主社(いのちぬしのやしろ)の背後の大岩の下から、長さ約30センチの銅戈とともに、長さ35ミリほどで、世にも美しい新潟の糸魚川産の翡翠の勾玉が見つかっています。
 引用元:ことりっぷ
引用元:ことりっぷ古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)
八千矛の神の歌物語
この八千矛の神、高志の國の沼河比賣を婚はむとして幸でます時に、その沼河比賣の家に到りて歌よみしたまひしく、
- 八千矛の神(多くの武器のある神の義。大国主の神の別名。)
- 高志の國の沼河比賣(北越の沼河の地の姫。ヌナカハは今の糸魚川町附近だという)
- 家に到りて(男子が夜間女子の家を訪れるのが古代の婚姻の風習である)
八島國 妻求ぎかねて、
遠遠し 高志の國に
賢し女を ありと聞かして、
麗し女を ありと聞こして、
さ婚ひに あり立たし
婚ひに あり通はせ、
大刀が緒も いまだ解かずて、
襲をも いまだ解かね、
孃子の 寢すや板戸を
押そぶらひ 吾が立たせれば、
引こづらひ 吾が立たせれば、
青山に鵼は鳴きぬ。
さ野つ鳥 雉子は響む。
庭つ鳥 鷄は鳴く。
うれたくも 鳴くなる鳥か。
この鳥も うち止めこせね。
いしたふや 天馳使、
- さ婚ひに あり立たし(ヨバヒは、呼ぶ義で婚姻を申し入れる意。サは接頭語。アリタタシは、お立ちになって。動詞の上につけるアリは在りつつの意。タタシは立つの敬語)
- 襲をも いまだ解かね(オスヒをもまだ解かないのに。オスヒは通例の服裝の上に着る衣服。礼装、旅装などに使用する。トカネは解かないのにの意)
- 寢すや(ナスは寝るの敬語。ヤは感動の助詞で調子をつけるために使う)
- 押そぶらひ(押しゆすぶって)
- 鵼(現在は、トラツグミという鳥。夜間に飛んで鳴く)
- うれたくも(歎かわしいことに)
- いしたふや(イ下フで、下方にいる意だろう。イは接頭語。ヤは感動の助詞)
- 天馳使(走り使いをする部族。アマは神聖なの意につける。この種の歌を語り伝える部族)
- こをば(この事をば。この通りです)
ぬえくさの 女にしあれば、
吾が心 浦渚の鳥ぞ。
今こそは 吾鳥にあらめ。
後は 汝鳥にあらむを、
命は な死せたまひそ。
いしたふや 天馳使、
事の 語りごとも こをば。 (歌謠番號三)
ぬばたまの 夜は出でなむ。
朝日の 咲み榮え來て、
㭳綱の 白き腕
沫雪の わかやる胸を
そ叩き 叩きまながり
眞玉手 玉手差し纏き
股長に 寢は宿さむを。
あやに な戀ひきこし。
八千矛の 神の命。
かれその夜は合はさずて、明日の夜御合したまひき。
またその神の嫡后須勢理毘賣の命、いたく嫉妬みしたまひき。かれその日子ぢの神侘びて、出雲より倭の國に上りまさむとして、裝束し立たす時に、片御手は御馬の鞍に繋け、片御足はその御鐙に蹈み入れて、歌よみしたまひしく、
- ぬえくさの(比喩による枕詞。なえた草のような)
- 浦渚の鳥ぞ(水鳥です。おちつかない比喩)
- な死せたまひそ(おなくなりなさるな)
- ぬばたまの(比喩による枕詞。カラスオウギの実は黒いから夜に冠する)
- 㭳綱の(同前。楮で作った綱は白い)
- 沫雪の(同前。アワのような大きな雪)
- あやに な戀ひきこし(たいへんに恋をなさいますな)
- 嫉妬み(第二の妻に対する憎しみ)
- 日子ぢの神(夫の神)
まつぶさに 取り裝ひ
奧つ鳥 胸見る時、
羽たたぎも これは宜はず、
邊つ浪 そに脱き棄て、
鴗鳥の 青き御衣を
まつぶさに 取り裝ひ
奧つ鳥 胸見る時、
羽たたぎも こも宜はず、
邊つ浪 そに脱き棄て、
山縣に 蒔きし あたねつき
染木が汁に 染衣を
まつぶさに 取り裝ひ
奧つ鳥 胸見る時、
羽たたぎも 此しよろし。
いとこやの 妹の命、
群鳥の 吾が群れ往なば、
引け鳥の 吾が引け往なば、
泣かじとは 汝は言ふとも、
山跡の 一本すすき
項傾し 汝が泣かさまく
朝雨の さ霧に立たむぞ。
若草の 嬬の命。
- 取り装ひ(十分に着用して)
- 奧つ鳥(比喩による枕詞。水鳥のように胸をつき出して見る)
- 羽たたぎ(奧つ鳥と言ったので、その縁でいう。身のこなし)
- 鴗鳥(比喩による枕詞。カワセミ。青い鳥)
- 山縣(山の料地)
- あたねつき(アタネは、アカネに同じというが不明。アカネはアカネ科の蔓草。根をついてアカネ色の染料をとる)
- いとこやの(イトコは親愛なる人。ヤは接尾語)
- 妹の命(女子の敬称)
- 群鳥の(比喩による枕詞)
- 引け鳥(同前。空とおく引き去る鳥)
- 項傾し(首をかしげて。うなだれて)
- 汝が泣かさまく(お泣きになることは。マクは、ムコトに相当する)
- さ(真福寺本は、サに當る字が無い)
- 若草の(比喩による枕詞)
吾が大國主。
汝こそは 男にいませば、
うち廻る 島の埼埼
かき廻る 磯の埼おちず、
若草の 嬬持たせらめ。
吾はもよ 女にしあれば、
汝を除て 男は無し。
汝を除て 夫は無し。
文垣の ふはやが下に、
蒸被 柔が下に、
㭳被 さやぐが下に、
沫雪の わかやる胸を
㭳綱の 白き臂
そ叩き 叩きまながり
ま玉手 玉手差し纏き
股長に 寢をしなせ。
豐御酒 たてまつらせ。 (歌謠番號六)
- うち廻【み】る(このミルは、原文「微流」。微は、古代のミの音声二種のうちの乙類に属し、甲類の見るのミの音声と違う。それで廻る意であり、ここは廻っているの意)
- 島(シマは水面に臨んだ土地。はなれ島には限らない)
- 磯の埼おちず(磯の突端のどこでも)
- 嬬持たせらめ(お持ちになっているでしよう。モタセ、持ツの敬語の命令形。ラ、助動詞の未然形。メ、助動詞ムの已然形で、上の係助詞コソを受けて結ぶ)
- 汝を除て(汝をおいては)
- 文垣の ふはやが下に(織物のトバリのふわふわした下で)
- 蒸被 柔が下に(あたたかい寝具のやわらかい下で)
- 㭳被 さやぐが下に(楮の衾【ふすま/布団】のざわざわする下で)
- そ叩き 叩きまながり(叩いて抱きあい)
- たてまつらせ(めしあがれ。奉るの敬語の命令形)
- 盞結ひして(酒盃をとりかわして約束して)
- 項懸けりて(首に手をかけて)
- 神語(以上の歌の名称で、以下この種の名称が多く出る。これは歌曲として伝えられたのでその歌曲としての名である。この八千矛の神の贈答の歌曲は舞を伴なっていたらしい)