古事記現代語訳(48)木梨之軽と軽大郎女の禁断の恋
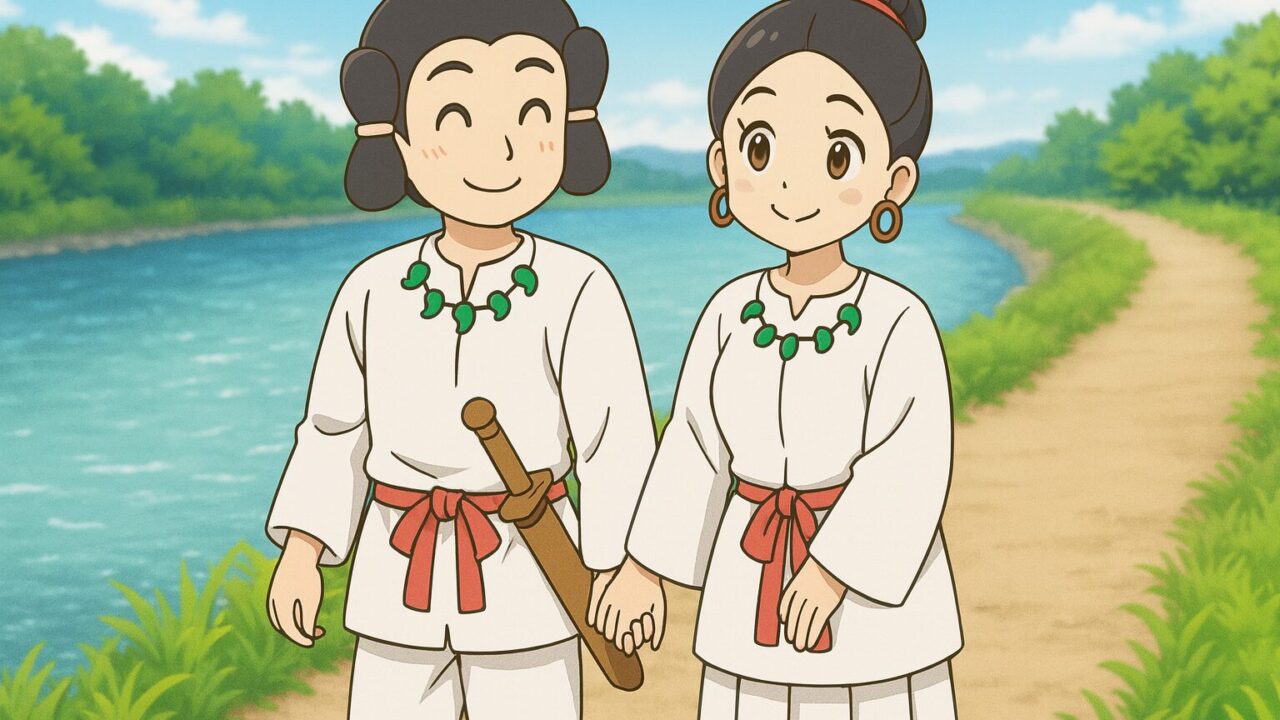
天皇の後継者、木梨之軽皇子の大スキャンダル
允恭天皇がお隠れになった後には、長男の木梨之軽(きなしのかる)皇子が帝位につくことに決まっておりました。

ところが、軽皇子はご即位なさる前に、同じ母を持つ妹の軽大郎女(かるのおおいらつめ)と、禁断の恋に落ちてしまいました。

軽大郎女は、またの名を衣通郎女(そとおしのいらつめ)といいました、そのお身体から発する光が衣を通してもわかるほど輝いていたからです。

軽皇子は妹に、
「山に田を作ったが、その山が高いので樋(ひ)を通した。その樋のように、ひそかに通って求めた妻、人目を忍び、心で泣いている妻を、今夜私は手に入れたのだ」
と歌い、
さらに、
「笹の葉に霰が落ちてダシダシと音を立てるように、確かに確かに妻と添い寝した。人にそしられようが構わない」

「敷物の薦草(こもぐさ)が乱れても、妻と共寝をしたのだから、もうどうなってもかまわない」

と熱烈に歌い、兄妹の仲が公になってしまいました。
当時は、異母兄妹の恋愛や婚姻は認められていましたが、一緒に育った同母兄妹の恋愛や婚姻は、現在と同じく忌み嫌われるものでした。
樋(ひ)を通すとは、地下に木で水の流れる道を作ることです。
軽皇子と軽大郎女の恋は人々に大きな衝撃を与え、朝廷の官人ばかりか、民衆さえも後ろ指をさすようになってしまいました。

そういうわけで、皆が次第に弟の穴穂御子(あなほのみこ)、のちの第二十代、安康天皇を支持するようになっていったのです。

参照元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「安康天皇」
軽皇子、大前小前宿禰兄弟に匿われる
軽皇子は、自身の身に危険が迫るのを感じ、大前宿禰(おおまえのすくね)と小前宿禰(おまえのすくね)兄弟の家に逃げ込み、武器を作って備えました。

そのとき軽皇子が作った矢は軽い銅製で、「軽箭(かるや)」と呼ばれました。一方、穴穂御子もまた軍を整え、現在のものと同じ鉄製の矢「穴穂箭(あなほや)」を準備しました。

やがて穴穂御子の軍勢が大前小前宿禰の家を取り囲んだとき、突然雹が降り出しました。

穴穂御子は、
「大前小前宿禰の門の陰に集まろう!俺たちの力で雹を止ませよう!」
と歌って軍を鼓舞しました。
そこへ兄弟が、手を打ち、膝を打って、舞い踊りながら現れ、

「宮人の袴の鈴が落ちた程度のことに、どうしてそんなに騒ぎ立てるのですか?宮人も里人も、そんなことで騒がないでくださいよ」
と歌い、穴穂御子に向かって、
「同じ両親を持つ兄上を攻めれば世間の笑いものになります。私どもが捕えて差し出します」
と言いました。
穴穂御子は軍を退かせ、やがて兄弟は軽皇子を連れてきました。

捕らえられた軽皇子は、妹の軽大郎女を思い、

「空を飛ぶ雁よ、軽のお嬢さん。そんなに泣くと人に気づかれるよ。波佐の山の鳩のように、忍び泣くがよい」
「空を飛ぶ雁よ、軽のお嬢さん。しっかりと寄り添ってともに寝ましょう」
と歌いました。
大前宿禰と小前宿禰兄弟は、物部氏です。実の兄弟かどうかは不明です。
波佐の山の場所は不明。兵庫県宍粟市には、標高1,191メートルの波佐利山があります。
島流しの刑
穴穂御子は軽皇子を伊予の道後温泉に流すことにしました。

愛媛県松山市の道後温泉は、日本最古の温泉地の一つで、古事記だけではなく、源氏物語にも登場します。

さらに、軽皇子が流される前に歌われた歌は、

「空を飛ぶ鳥は私の使者です。鶴の鳴き声が聞えた時は、妻よ、私の事をお尋ねなさい」
「私を島に流したら、船の片隅に乗って帰ってきてやろう。私の畳は動かさないように。「畳」と言ってはみたが、私の妻を護っていてくれということだ」

今度は、軽大郎女が歌を返しました。
「阿比泥(あいね)の浜辺の牡蠣の貝殻で足をお痛めなさらぬよう、どうぞお気をつけください」

と歌を贈り、とうとう恋しさに耐えきれず、兄の後を追って伊予へ向かおうと決められました。
「あなたが行ってから、長い時間が過ぎました。葉っぱが向かい合わせになっているこのニワトコの木のように、私がお迎えに参ります。待っていることなんてできないのです」

軽皇子は妹と再会して、
「泊瀬の山の大きな峰と小さな峰に旗を立て、愛しい妻よ、寝ても覚めてもおまえを思っているよ」

「泊瀬の川の上流に神聖な杭を打ち、下流にも立派な杭を打ち、それぞれに鏡と玉を掛けるように、私の美しい妻こそ、鏡のように、玉のように大切な人だ。その人がいるというのなら、どこにでも行きましょう、どの場所も愛しましょう。」
と歌い、二人は固く結ばれました。
「私の畳は動かさないように」については、人が去った跡を動かすと、その人が帰って来ないという言い伝えがあったそうです。
阿比泥の浜辺の場所は不明。相寝でしょうか。
ニワトコの木は、別名セッコツボク(接骨木)。名前の由来は、枝や幹を煎じて水あめ状にしたものを、骨折の治療の際の湿布剤に用いたことから。
泊瀬の山・泊瀬の川は、奈良県桜井市初瀬。泊瀬朝倉宮は、第二十一代雄略天皇が営んだ宮殿です。初瀬山には西国三十三所第八番の長谷寺があります。初瀬川は歌枕で、『万葉集』では13首が詠まれています。歌枕とは、和歌によく登場する、由緒ある特定の地名や名所のことです。ほかには、龍田川、宇治、吉野山、塩竈、逢坂があります。
川の中に杭を打って、玉や鏡を掛けるのは、神を招いて穢を祓うためです。
しかしその恋は叶うことなく、やがて二人はともにその地で命を絶ちました。
ちなみに、日本書紀では、妹の軽大郎女の方が、伊予に流され、残された木梨之軽が一人で死を選んだとなっています。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)
木梨の輕の太子
天皇崩りまして後、木梨の輕の太子、日繼知らしめすに定まりて、いまだ位に即きたまはざりしほどに、その同母妹輕の大郎女に姧けて、歌よみしたまひしく、
山高み 下樋をわしせ、
下娉ひに 吾が娉ふ妹を、
下泣きに 吾が泣く妻を、
昨夜こそは 安く肌觸れ。 (歌謠番號七九)
こは志良宜歌なり。また歌よみしたまひしく、
たしだしに 率寢てむ後は
人は離ゆとも。 (歌謠番號八〇)
うるはしと さ寢しさ寢てば
刈薦の 亂れば亂れ。
さ寢しさ寢てば。 (歌謠番號八一)
こは夷振の上歌なり。
- 日繼知らしめすに定まりて(帝位につくべきと決まって)
- 姧け(異母の兄弟の婚姻はさしつかえないが、同母の場合は不倫とされる)
- あしひきの(枕詞。語義不明)
- 下樋をわしせ(地下に木で水の流れる道を作って。以上比喩による序)
- 下娉ひに 吾が娉ふ妹を(人に知らせないで密かに問い寄る妻)
- 下泣きに 吾が泣く妻を(心の中で泣いている妻)
- 昨夜(この夜。今過ぎて行く夜)
- 志良宜歌(歌曲の名。しり上げ歌の意という)
- うつや霰の(以上、比喩による序。ヤは感動の助詞)
- たしだしに(たしかに、しかと)
- 人は離ゆとも(あの子は別れてもしかたがない)
- うるはしと(愛する人と)
- 刈薦の(枕詞)
- 夷振の上歌(歌曲の名)
ここを以ちて百の官また、天の下の人ども、みな輕の太子に背きて、穴穗の御子に歸りぬ。ここに輕の太子畏みて、大前小前の宿禰の大臣の家に逃れ入りて、兵を備へ作りたまひき。(その時に作れる矢は、その箭の同を銅にしたり。かれその矢を輕箭といふ。)穴穗の御子も兵を作りたまひき。(その王子の作れる矢は、今時の矢なり。そを穴穗箭といふ。)穴穗の御子軍を興して、大前小前の宿禰の家を圍みたまひき。ここにその門に到りましし時に大氷雨降りき。かれ歌よみしたまひしく、
かな門陰 かく寄り來ね。
雨立ち止めむ。 (歌謠番號八二)
ここにその大前小前の宿禰、手を擧げ、膝を打ち、舞ひかなで、歌ひまゐ來。その歌、
落ちにきと 宮人とよむ。
里人もゆめ。 (歌謠番號八三)
この歌は宮人曲なり。
かく歌ひまゐ來て、白さく、「我が天皇の御子、同母兄の御子をな殺せたまひそ。もし殺せたまはば、かならず人咲はむ。僕捕へて獻らむ」とまをしき。ここに軍を罷めて退きましき。かれ大前小前の宿禰、その輕の太子を捕へて、率てまゐ出て獻りき。その太子、捕はれて歌よみしたまひしく、
いた泣かば 人知りぬべし。
波佐の山の 鳩の、
下泣きに泣く。 (歌謠番號八四)
また歌よみしたまひしく、
したたにも 倚り寢てとほれ。
輕孃子ども。 (歌謠番號八五)
かれその輕の太子をば、伊余の湯に放ちまつりき。また放たえたまはむとせし時に、歌よみしたまひしく、
鶴が音の 聞えむ時は、
吾が名問はさね。 (歌謠番號八六)
この三歌は、天田振なり。
また歌よみしたまひしく、
- 穴穗の御子(安康天皇)
- 大前小前の宿禰(物部氏。大前と小前との二人である)
- 同(胴に同じ。矢の柄。但し異説がある)
- 門(堅固な門)
- 舞ひかなで(舞い躍って)
- 足結の小鈴(袴を結ぶ紐につけた鈴)
- 宮人とよむ(宮廷の人が立ち騒ぐ)
- 里人もゆめ(里の人も騒ぐな。宮人が騒いでいるが、そんなに騷ぎを大きくするな)
- 宮人曲(歌曲の名)
- 我が天皇の御子(天皇である皇子樣)
- 天飛む(枕詞。天飛ぶ雁の意に、カルの音に冠する)
- 波佐の山(所在不明)
- 鳩の(鳩のように)
- したたにも(したたかに。しっかりと)
- 倚り寢てとほれ(寄り寝て行き去れ)
- 伊余の湯(愛媛県の松山市の温泉地。道後温泉)
- 天田振(歌曲の名。歌詞によって名づける)
船餘り い歸りこむぞ。
吾が疊ゆめ。
言をこそ 疊と言はめ。
吾が妻はゆめ。 (歌謠番號八七)
この歌は、夷振の片下なり。その衣通の王、歌獻りき。その歌、
蠣貝に 足踏ますな。
明してとほれ。 (歌謠番號八八)
かれ後にまた戀慕に堪へかねて、追ひいでましし時、歌ひたまひしく、
山たづの 迎へを行かむ。
待つには待たじ。(ここに山たづといへるは、今の造木なり) (歌謠番號八九)
かれ追ひ到りましし時に、待ち懷ひて、歌ひたまひしく、
大尾には 幡張り立て、
さ小尾には 幡張り立て、
大尾よし ながさだめる
思ひ妻あはれ。
槻弓の 伏る伏りも、
梓弓 立てり立てりも、
後も取り見る 思ひ妻あはれ。 (歌謠番號九〇)
また歌ひたまひしく、
上つ瀬に 齋杙を打ち、
下つ瀬に ま杙を打ち、
齋杙には 鏡を掛け、
ま杙には ま玉を掛け、
ま玉なす 吾が思ふ妹、
鏡なす 吾が思ふ妻、
ありと いはばこそよ、
家にも行かめ。國をも偲はめ。 (歌謠番號九一)
かく歌ひて、すなはち共にみづから死せたまひき。かれこの二歌は讀歌なり。
- 船餘り(その船の余地で)
- 吾が疊ゆめ(わたしの座所をそのままにしておけ。タタミは敷物。人の去った跡を動かすと、その人が帰って来ないとする思想がある)
- 吾が妻はゆめ(わたしの妻に手をつけるな)
- 夷振の片下(歌曲の名)
- 衣通の王(軽の大郎女)
- 夏草の(叙述による枕詞)
- あひねの濱(所在不明)
- 明してとほれ(夜が明けてからいらっしゃい)
- け長くなりぬ(時久しくなった)
- 山たづの(枕詞。次に説明があるが、それでも明らかでない。ヤマタヅは、樹名今のニワトコで、葉が対生ているから、ムカヘに冠するという。「君が行きけ長くなりぬ山たづね迎へか行かむ待ちにか待たむ」(万葉集))
- 迎へを行かむ(ヲは間投の助詞)
- 隱國の(枕詞。山に包まれている所の意)
- 泊瀬の山(奈良県磯城郡)
- 大尾(ヲは高い土地)
- さ小尾(サは接頭語。大尾と共にあちこちの高みのところに。以上、次の句の序)
- 大尾(語義不明。上の大尾にと同語を繰り返してオヨソの意を現すか、または別の副詞か)
- ながさだめる(あなたの妻ときめた。動詞定むが四段活になっている)
- 槻弓の(枕詞。槻の木の弓)
- 伏る伏りも(伏しても。転がる意の動詞コユが再活して、伏しまろぶ意にコヤルと言っている)
- 梓弓(枕詞)
- 後も取り見る(後も近く見る)
- 齋杙(清浄の杙。祭を行うために杙をうつ)
- ま玉を掛け(以上序で、次の玉と鏡の二つの枕詞を引き出す。川中に柱を立てて玉や鏡を懸けるのは、これによって神を招いて穢を祓うのである。「こもりくの泊瀬の川の、上つ瀬に斎杙【いくひ】を打ち、下つ瀬にま杙を打ち、斎杙には鏡をかけ、ま杙にはま玉をかけ、ま玉なすわが念ふ妹も、鏡なすわが念ふ妹も、ありと言はばこそ、国にも家にも行かめ、誰が故か行かむ」(萬葉集))
- 讀歌(歌曲の名)














