古事記現代語訳(37)神功皇后の母方の祖先
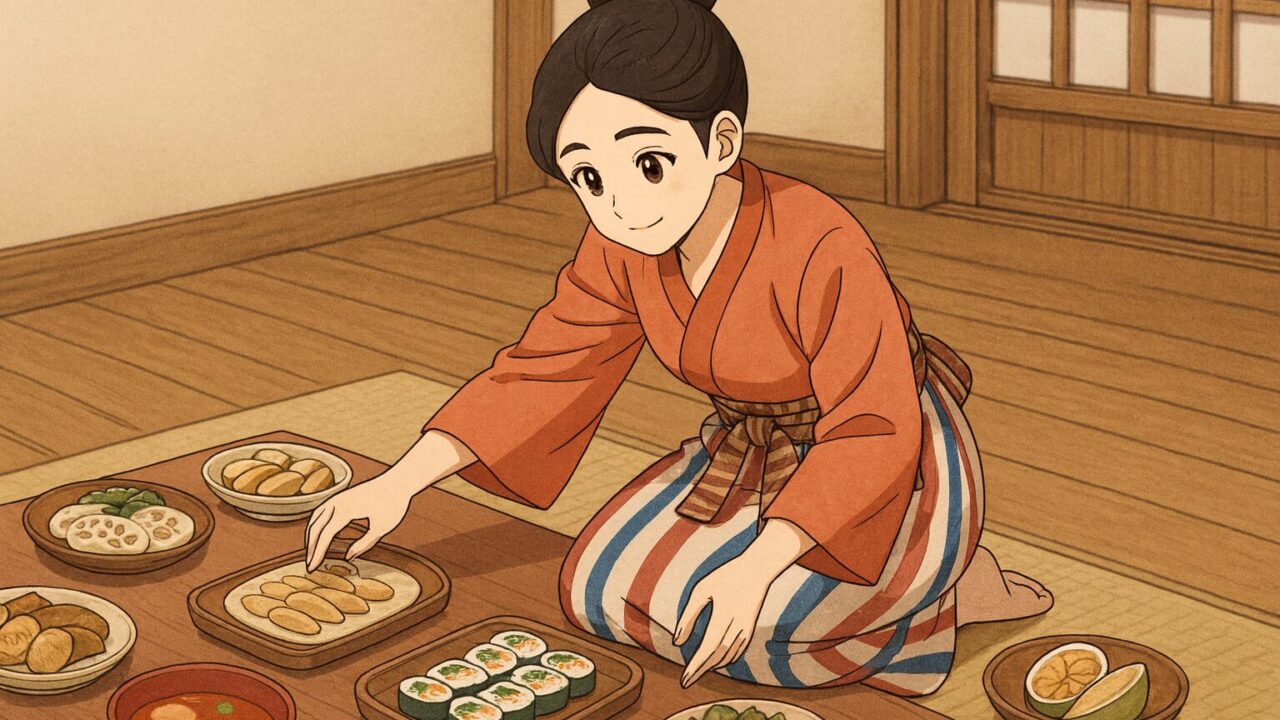
応神天皇の母上である神功皇后の母方のご先祖については、次のようなお話が伝わっています。

むかし新羅の国に、阿具沼(あぐぬま)という大きな沼がありました。

ある日、その沼のほとりで、一人の女性が昼寝をしていると、不思議なことに、日の光が虹のようになって、その女性のお腹にさっと射しこみました。

通りかかった一人の農夫がその様子を見て、「これは、なんと不思議なことだ!」と思い、それから折にふれて女性の様子を見守っていました。
すると、女性はまもなく身ごもり、一つの赤い玉を生み落としました。農夫はその玉をもらい受け、布に包んでいつも腰につけていました。

ある日、その農夫が谷間の田畑で働く人々の食べ物を牛に背負わせて運んでいると、新羅の国王の皇子・天之日矛(あめのひほこ)に会いました。

天之日矛は農夫を怪しんで、「おまえ、その牛を殺して食べるつもりだろう」と責め立て、その農夫を捕らえて牢に入れようとしました。
農夫が必死に弁明しましたが、聞き入れてもらえません。そこで仕方なく、腰に下げていた赤い玉を差し出しました。

天之日矛は農夫を赦し、その玉を持ち帰って床の間に飾りました。

するとその玉は、たちまち一人の美しい乙女に姿を変えました。

天之日矛はその乙女を妻として迎えました。
妻は毎日、さまざまな珍しいお料理を作り、夫に尽くしましたが、夫は次第に、驕り高ぶるようになり、妻を罵るようになりました。

妻はついに堪えかねて、
「私は本来、あなたのような人の妻になるような女ではありません。母の国に帰らせていただきます」
ときっぱり言い放ち、小舟に乗って、摂津の難波の津にたどり着きました。

この女性は難波の比売碁曽(ひめこそ)の社においでになる阿加流比売(あかるひめ)という女神でした。

現在、大阪市東成区の比売許曽神社は、阿加流比売ではなく、大国主神と多紀理毘売命(たぎりひめのみこと)の娘である下照比売(したてるひめ)を祀っています。
阿加流比売は、大阪市平野区の杭全神社(くまたじんじゃ)の境外末社、赤留比売命神社(あかるひめのみことじんじゃ)や、大阪市西淀川区の姫嶋神社で祀られています。
 引用元:じゃらんnet
引用元:じゃらんnetとくに姫嶋神社は、「やり直し神社」とも呼ばれ、とくに離婚や転職で、人生やりなおししたい人々を新しい門出へと導いてくれる神社として有名です。
 引用元:ええやん!大阪商店街
引用元:ええやん!大阪商店街天之日矛は妻を追いかけて海を渡ろうとしましたが、海の神に阻まれて難波にはたどり着けず、やむなく但馬の国へ回り、そこに住みつきました。

そこで遅摩之俣尾(たじまのまたお)の娘、前津見(まえつみ)を妻とし、その子孫は代々続きました。

その後裔の一人に、多遅摩毛理(たじまもり)があり、彼は垂仁天皇の命を受けて常世国へと渡り、時じくの香の木の実、今でいう橘の実を探し求め、持ち帰ってきた人物として知られています。

但馬の国は現在の兵庫県北部です。


また、天之日矛から七代目の孫にあたる高額比売命(たかぬかひめ)が、息長帯比売命(おきながたらしひめのみこと)つまり、神功皇后のお母さまとなられました。

神功皇后と阿加流比売は、まったく無関係のようです。残念です。

天之日矛が日本に渡来したとき、彼は八種の宝物を携えていました。

玉を連ねた玉津宝(たまつたから)二つ、振浪領巾(なみふるひれ)、切浪領巾(なみきるひれ)、振風領巾(かぜふるひれ)、切風領巾(かぜきるひれ)、奥津鏡(おきつかがみ)、辺津鏡(へつかがみ)、これらを合わせて八種の宝といいます。
これらはのちに、出石八前大神(いずしやまえのおおかみ)として、出石神社に祀られることになりました。
 引用元:豊岡市観光サイト
引用元:豊岡市観光サイト振浪領巾、切浪領巾、振風領巾、切風領巾、以上四種のヒレは、風や波を起し、また鎮める力のあるもの。
「浪振る」は浪を起す。「浪切る」は浪を鎮める、「風」も同じ。ヒレは、女性が首にかける白い織物です。これを振ることによって威力が発生します。

奥津鏡、辺津鏡、以上二種の鏡は、海上の平安を守る鏡。オキツは海上遠く、ヘツは海辺のことです。

出石八前大神と天之日矛は、出石神社の御祭神となっています。
現在、兵庫県豊岡市の出石神社は、但馬における一宮(いちのみや)神社ということで「いっきゅうさん」の名で親しまれ、ここに天之日矛が祀られています。境内には、禁則地があり、入ると祟りがあるとされるので注意が必要です。

成務天皇、仲哀天皇、神功皇后のお三方は、架空の人物という説もありますが、「日本書紀」では、神功皇后の項目だけで一巻を割いています。なので、朝鮮半島への遠征や神懸かりの話はともかく、神功皇后という女性は実在したのではないかという説が有力です。

また、神功皇后は、邪馬台国の女王卑弥呼、またはその後継者の台与(とよ)ではないかとする説もあります。

卑弥呼については、崇神天皇の皇女「豊鉏入日売命」、邇邇芸命の母の「万幡豊秋津師比売命(よろづはたとよあきつしひめのみこと)」、第7代孝霊天皇の皇女「母母曽毘売(ももそひめ)」など、様々な説があります。

古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)
天の日矛
また昔新羅の國主の子、名は天の日矛といふあり。この人まゐ渡り來つ。まゐ渡り來つる故は、新羅の國に一つの沼あり、名を阿具沼といふ。この沼の邊に、ある賤の女晝寢したり。ここに日の耀虹のごと、その陰上に指したるを、またある賤の男、その状を異しと思ひて、恆にその女人の行を伺ひき。かれこの女人、その晝寢したりし時より、姙みて、赤玉を生みぬ。ここにその伺へる賤の男、その玉を乞ひ取りて、恆に裹みて腰に著けたり。この人、山谷の間に田を作りければ、耕人どもの飮食を牛に負せて、山谷の中に入るに、その國主の子天の日矛に遇ひき。ここにその人に問ひて曰はく、「何ぞ汝飮食を牛に負せて山谷の中に入る。汝かならずこの牛を殺して食ふならむ」といひて、すなはちその人を捕へて、獄内に入れむとしければ、その人答へて曰はく、「吾、牛を殺さむとにはあらず、ただ田人の食を送りつらくのみ」といふ。然れどもなほ赦さざりければ、ここにその腰なる玉を解きて、その國主の子に幣しつ。かれその賤の夫を赦して、その玉を持ち來て、床の邊に置きしかば、すなはち顏美き孃子になりぬ。仍りて婚して嫡妻とす。ここにその孃子、常に種種の珍つ味を設けて、恆にその夫に食はしめき。かれその國主の子心奢りて、妻を詈りしかば、その女人の言はく、「およそ吾は、汝の妻になるべき女にあらず。吾が祖の國に行かむ」といひて、すなはち竊びて小船に乘りて、逃れ渡り來て、難波に留まりぬ。(こは難波の比賣碁曾の社にます阿加流比賣といふ神なり。)
- 天の日矛(日本書紀では垂仁天皇の巻にあり、播磨國風土記では、葦原シコヲの命との交渉を記している)
- 赤玉を生みぬ(卵生説話の一つ。その玉が乙女に化したとする。この点からいえば神婚説話であって、外来の形を伝えていると見られるのが注意される)
- 難波の比賣碁曾(大阪市東成区)
ここに天の日矛、その妻の遁れしことを聞きて、すなはち追ひ渡り來て、難波に到らむとする間に、その渡の神塞へて入れざりき。かれ更に還りて、多遲摩の國に泊てつ。すなはちその國に留まりて、多遲摩の俣尾が女、名は前津見に娶ひて生める子、多遲摩母呂須玖。これが子多遲摩斐泥。これが子多遲摩比那良岐。これが子多遲摩毛理、次に多遲摩比多訶、次に清日子三柱。この清日子、當摩の咩斐に娶ひて生める子、酢鹿の諸男、次に妹菅竈由良度美、かれ上にいへる多遲摩比多訶、その姪由良度美に娶ひて生める子、葛城の高額比賣の命。(こは息長帶比賣の命の御祖なり。)
かれその天の日矛の持ち渡り來つる物は、玉つ寶といひて、珠二貫、また浪振る比禮、浪切る比禮、風振る比禮、風切る比禮、また奧つ鏡、邊つ鏡、并はせて八種なり。(こは伊豆志の八前の大神なり。)
- 多遲摩の國(兵庫県の北部)
- 多遲摩毛理(垂仁天皇の御代に常世の国に行って橘【時じくの香の木の実】を持って来た人)
- 息長帶比賣の命(神功皇后)
- 玉つ寶といひて、珠二貫(珠を緒に貫いたもの二つ)
- 浪振る比禮、浪切る比禮、風振る比禮、風切る比禮(以上四種のヒレは、風や波を起し、また鎮める力のあるもの。浪振るは浪を起す。浪切るは浪を鎮める。風も同様。ヒレは、白い織物で女子が首にかける。これを振ることによって威力が発生する。)
- 奧つ鏡、邊つ鏡(二種の鏡は、海上の平安を守る鏡。オキツは海上遠く、ヘツは海辺)
- 伊豆志の八前の大神(兵庫県出石郡の出石神社)















