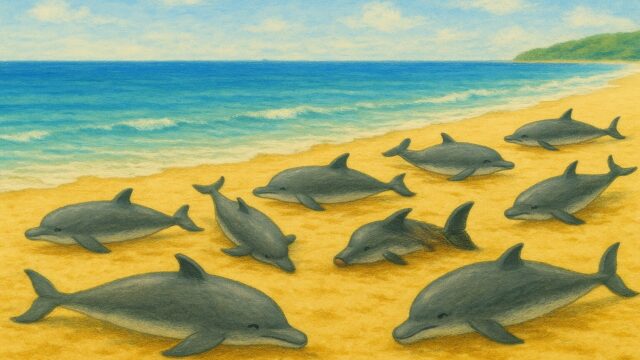古事記現代語訳(34)仲哀天皇の死と神功皇后の新羅遠征

神功皇后の神懸かりと仲哀天皇の急逝
帯中津日子命(たらしなかつひこのみこと)、第十四代、仲哀天皇は、穴門豊浦宮(あなとのとよらのみや)と筑紫香椎宮(つくしのかしいのみや)において天下をお治めになりました。

穴門豊浦宮は、現在の山口県下関市長府宮の内町、忌宮神社(いみのみやじんじゃ)の場所にあり、筑紫香椎宮は福岡市東区香椎の神社、香椎宮(かしいぐう)の場所にあります。


忌宮神社は仲哀天皇と神功皇后と応神天皇、香椎宮は仲哀天皇と神功皇后をお祀りしています。
仲哀天皇の御代、秦の始皇帝の子孫である功満王(こまおう)が渡来して日本に住みつき、珍しい蚕(かいこ)の卵を奉献したことで、豊浦宮(現在の忌宮神社)が蚕種(さんしゅ)渡来の地とされています。蚕種は蚕の卵です。

皇后の息長帯比売命(おきながたらしひめのみこと)、神功皇后は、神懸かりをなさる方でした。

ある年、天皇は熊曽征伐のため筑紫香椎宮にお出ましになり、戦の手立てを神に問おうと、大臣の建内宿禰を祭場に据えて、ご自分は琴を弾かれました。

すると皇后に神が憑りつき、その口を借りてこう告げました。

「西の方に豊かな国がある。金銀をはじめ、数多の宝に満ちている。つまらぬ熊曽より、まずその国をお前に与えてやろう」

仲哀天皇は高台から西を望みましたが、果てしなく広がる海しか見えず、心の中で「これは嘘だ。神の偽物だ」と思い、琴を押し退け黙ってしまわれました。

すると神は怒り、
「この国はお前の治めるべき国ではない。お前はもう不要だ」
と告げました。
建内宿禰は慌てて「恐れ多いことです、陛下、どうか琴をお弾きください」と諫め、天皇はしぶしぶ再び弾かれましたが、まもなく琴の音は途絶え、灯を点してみると、天皇はすでに崩御されていたのです。
 皇后と宿禰は恐れおののき、まず亡骸を殯の宮(もがりのみや)に移し、国中の穢れを祓うため、生剥(いきはぎ)、逆剥(さかはぎ)、畦離(あはなち)、溝埋(みぞうめ)、屎戸(くそと)、上通下通婚(おやこたはけ)、馬婚(うまたはけ)、牛婚(うしたはけ)、鶏婚(とりたはけ)、犬婚(いぬたはけ)の罪を犯した者たちを探し出し、大祓を行い、国中の穢れをすっかりなくしておしまいになりました。
皇后と宿禰は恐れおののき、まず亡骸を殯の宮(もがりのみや)に移し、国中の穢れを祓うため、生剥(いきはぎ)、逆剥(さかはぎ)、畦離(あはなち)、溝埋(みぞうめ)、屎戸(くそと)、上通下通婚(おやこたはけ)、馬婚(うまたはけ)、牛婚(うしたはけ)、鶏婚(とりたはけ)、犬婚(いぬたはけ)の罪を犯した者たちを探し出し、大祓を行い、国中の穢れをすっかりなくしておしまいになりました。
殯の宮は、古代に行なわれていた葬儀の儀礼で、本葬するまでの期間、ご遺体を仮安置しておく場所です。
穢が生じたのは、さまざまな罪が犯されたからなので、まずその罪を洗い出します。
生剥(いきはぎ)から屎戸(くそと)までは、天照大御神に誓約(うけい)で勝ち、図に乗った須佐之男命の乱暴行為の中に出てきました。

生剥や逆剥は、馬の皮をむく罪。屎戸は、汚いものを清浄な場所に撒き散らす罪。上通下通婚以下は、近親婚や動物婚など、不倫の婚姻行為です。

仲哀天皇は五十二で崩御され、御陵は河内の恵賀の長江にあります。
河内の恵賀の長江は、藤井寺市藤井寺の「岡ミサンザイ古墳」に治定されています。全長245メートルの前方後円墳。「ミサンザイ」は「ミササギ(陵)」の転訛です。

仲哀天皇は実在を疑われており、「岡ミサンザイ古墳」は、第21代の雄略天皇の御陵だという説もあります。
そこで改めて神意を伺うと、神は「この国は皇后のお腹にいる御子が治めるべきである」と告げました。

建内宿禰が御子の性別を問うと「男の御子だ」と答え、さらに「あなたさまはどなたでいらっしゃいますか?」と尋ねると「これは天照大御神の御心だ。ほかには、底筒男命、中筒男命、上筒男命の三神である」と明かしました。この三神は、住吉大社の御祭神です。

神はさらに征伐の手順を授けました。
「もしその国を得ようと思うなら、天地、山、海、河の神々に供え物を捧げ、我々の御魂を船上に祀れ。魔よけのために槇を焼いた灰を瓢箪に入れ、箸や木の葉の皿を多く作り、それらを大海に散らして渡りなさい」

神功皇后の新羅遠征
皇后は教えの通りに軍勢を整え、数多の船を並べて出陣しました。

すると海中の魚たちが船を背に負い、強い追い風が吹いて船団は一気に進み、新羅の国へと押し寄せました。

大波は津波となって国の半ばにまで達し、軍勢はその勢いのまま攻め込みました。

恐れた新羅の王は平伏し、
「これより永遠に天皇にお仕えし、馬飼いとなり、船の腹や棹の乾く暇もなく貢ぎ続けましょう」

と誓いました。
そしてその印に、お杖を、新羅の王宮の門に突き刺しておきました。

こうして新羅の王を馬飼いと定め、百済を渡海の拠点とし、さらに住吉の大神の荒御魂をこの国の守り神として祀り、威風堂々と凱旋されました。

大阪の住吉大社は、このとき神功皇后に神託を降ろし、新羅遠征を助けたとされる、底筒男命、中筒男命、上筒男命、そして神功皇后を御祭神とし、今もその御神徳を伝えています。

『日本書紀』には、新羅が朝貢してこなかったため、朝鮮遠征は、二度あったと記載されています。
古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)
六.仲哀天皇
神功皇后
帶中つ日子の天皇、穴門の豐浦の宮また筑紫の訶志比の宮にましまして、天の下治らしめしき。
その太后息長帶日賣の命は、當時神歸せしたまひき。かれ天皇筑紫の訶志比の宮にましまして熊曾の國を撃たむとしたまふ時に、天皇御琴を控かして、建内の宿禰の大臣沙庭に居て、神の命を請ひまつりき。ここに太后、神歸せして、言教へ覺し詔りたまひつらくは、「西の方に國あり。金銀をはじめて、目耀く種種の珍寶その國に多なるを、吾今その國を歸せたまはむ」と詔りたまひつ。ここに天皇、答へ白したまはく、「高き地に登りて西の方を見れば、國は見えず、ただ大海のみあり」と白して、詐りせす神と思ほして、御琴を押し退けて、控きたまはず、默いましき。ここにその神いたく忿りて、詔りたまはく、「およそこの天の下は、汝の知らすべき國にあらず、汝は一道に向ひたまへ」と詔りたまひき。ここに建内の宿禰の大臣白さく、「恐し、我が天皇。なほその大御琴あそばせ」とまをす。ここにややにその御琴を取り依せて、なまなまに控きいます。かれ、幾時もあらずて、御琴の音聞えずなりぬ。すなはち火を擧げて見まつれば、既に崩りたまひつ。
- 帶中つ日子の天皇(仲哀天皇)
- 穴門の豐浦の宮(山口県豊浦郡)
- 筑紫の訶志比の宮(福岡県糟屋郡香椎町)
- 息長帶日賣の命(神功皇后。開化天皇の系統)
- 當時神歸せ(神霊をよせて教を受けること)
- 沙庭(祭の場)
- 一道に向ひたまへ(ひたすらに一つの方向に進め)
ここに驚き懼みて、殯の宮にませまつりて、更に國の大幣を取りて、生剥、逆剥、阿離、溝埋、屎戸、上通下通婚、馬婚、牛婚、鷄婚、犬婚の罪の類を種種求ぎて、國の大祓して、また建内の宿禰沙庭に居て、神の命を請ひまつりき。ここに教へ覺したまふ状、つぶさに先の日の如くありて、「およそこの國は、汝命の御腹にます御子の知らさむ國なり」とのりたまひき。
- 殯の宮(葬る前に祭をおこなう宮殿)
- 國の大幣を取りて(穢が出来たので、それを浄めるために、その費用として筑紫の一国から品物を取り立てる。その産物などである)
- 生剥、逆剥、阿離、溝埋、屎戸、上通下通婚、馬婚、牛婚、鷄婚、犬婚の罪の類を種種求ぎて(穢を生じたのは、種々の罪が犯されたからであるから、まずその罪の類を求め出す。屎戸までは、岩戸の物語に出た。生剥逆剥は、馬の皮をむく罪。屎戸は、きたないものを清浄なるべき所に散らす罪。上通下通婚以下は、不倫の婚姻行為)
- 國の大祓(一国をあげての罪穢【つみけがれ】を祓う行事をして)
ここに建内の宿禰白さく、「恐し、我が大神、その神の御腹にます御子は何の御子ぞも」とまをせば、答へて詔りたまはく、「男子なり」と詔りたまひき。ここにつぶさに請ひまつらく、「今かく言教へたまふ大神は、その御名を知らまくほし」とまをししかば、答へ詔りたまはく、「こは天照らす大神の御心なり。また底筒の男、中筒の男、上筒の男三柱の大神なり。(この時にその三柱の大神の御名は顯したまへり。)今まことにその國を求めむと思ほさば、天つ神地つ祇、また山の神海河の神たちまでに悉に幣帛奉り、我が御魂を御船の上にませて、眞木の灰を瓠に納れ、また箸と葉盤とを多に作りて、皆皆大海に散らし浮けて、度りますべし」とのりたまひき。
- 底筒の男、中筒の男、上筒の男三柱の大神(住吉神社の祭神)
- 眞木の灰を瓠に納(木を焼いて作った灰をヒサゴ(蔓草の実、ユウガオ、ヒョウタンの類)に入れて。これは魔よけのためと解せられる)
- 葉盤(木の葉の皿。これは食物を与える意)
かれつぶさに教へ覺したまへる如くに、軍を整へ、船雙めて、度りいでます時に、海原の魚ども、大きも小きも、悉に御船を負ひて渡りき。ここに順風いたく起り、御船浪のまにまにゆきつ。かれその御船の波、新羅の國に押し騰りて、既に國半まで到りき。ここにその國主、畏ぢ惶みて奏して言さく、「今よ後、天皇の命のまにまに、御馬甘として、年の毎に船雙めて船腹乾さず、檝乾さず、天地のむた、退きなく仕へまつらむ」とまをしき。かれここを以ちて、新羅の國をば、御馬甘と定めたまひ、百濟の國をば、渡の屯家と定めたまひき。ここにその御杖を新羅の國主の門に衝き立てたまひ、すなはち墨江の大神の荒御魂を、國守ります神と祭り鎭めて還り渡りたまひき。
- 新羅の國(当時朝鮮半島の東部を占めていた国)
- 國主(朝鮮語で王または貴人をいう。コニキシともコキシともいう)
- 百濟の國(当時朝鮮半島の南部を占めていた国)
- 渡の屯家(渡海の役所)
- 荒御魂(神霊の荒い方面)