古事記現代語訳(56)意富祁王と袁祁王

後継者のいない清寧天皇
雄略天皇の御子、白髪大倭根子命(しらがのやまとねこのみこと)は第二十二代清寧天皇として、大和の磐余(いわれ)の甕栗(みかくり)の宮においでになり、天下をお治めになりました。
 引用元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「清寧天皇」
引用元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「清寧天皇」しかし清寧天皇は、生涯、皇后をお迎えになることなく、御子もお持ちになりませんでした。
そのためお名前を残すために「白髪部」を定められました。
皇居は、奈良県橿原市東池尻町の磐余甕栗宮(いわれのみかくりのみや)。場所は御厨子(みずし)神社周辺で、御陵は大阪府羽曳野市西浦にある「白髪山古墳」に治定されています。
 引用元:大和の神社
引用元:大和の神社 引用元:古墳マップ
引用元:古墳マップ清寧天皇は、『日本書紀』によると、出生時から髪の毛が白かったということです。父の雄略天皇は、そこに霊異を感じて皇太子にしたそうです。
清寧天皇には、お后も御子もなく、在位期間は4年間しかなく実績も記録されていないため、実在性を疑われています。40歳前後で崩御されたとされています。
清寧天皇には、御子がいらっしゃらなかったため、次に帝位を継ぐべきお方は見つからず、朝廷は大いに困りました。
ピンチヒッターは市辺之忍歯王の妹の飯豊王
人々は皇統の血筋を懸命に探し求めましたが、なかなか見当たらないので、一時的に雄略天皇に暗殺された市辺之忍歯王(いちのべのおしはのおう)の妹、忍海郎女(おしぬみのいらつめ)、またの名を飯豊王(いいとよのみこ)に、大和葛城の忍海(おしぬみ)の高木の角刺宮(つのさしのみや)で政(まつりごと)をお執りいただくことになりました。

大和葛城の忍海の高木の角刺宮は、忍海角刺宮(おしみつのさしのみや)と呼ばれ、現在の奈良県葛城市忍海(かつらぎしおしみ)にあったとされています。同地の角刺神社では、飯豊王をお祀りしています。飯豊はふくろうの意味。
 引用元:ならリビング.com
引用元:ならリビング.com存在していた市辺之忍歯王の御子たち
このときはまだ、市辺之忍歯王の御子である意富祁王(おおけのおう)と袁祁王(おけのおう)の兄弟二人が、播磨の国で牛飼いと馬飼いとなってひそかに生きながらえていることを、飯豊王はご存じなかったのです。

兄の意富祁王は第二十四代仁賢天皇で、弟の袁祁王は第二十三代顕宗(けんそう)天皇です。
 引用元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「仁賢天皇」
引用元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「仁賢天皇」 引用元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「顕宗天皇」
引用元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「顕宗天皇」
兄弟は、父上の市辺之忍歯王が、のちに雄略天皇になる大長谷若建命に暗殺されたという報せを受けて、命の危険を察知し、ただちに都を逃れました。これは、安康天皇が目弱王に暗殺された直後の出来事でした。


乾飯を盗まれた幼い兄弟
兄弟は、やがて山城の苅羽井(かりはい)に至り、乾飯(ほしいい)を食べようとしたところ、顔に前科者の印の入墨をした一人の老人が現れ、突然二人から乾飯を奪いました。
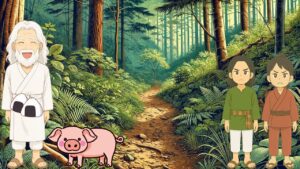
二人が「飯など惜しくはないが、お前は何者か」と問うと、老人は「俺は山城で豚を飼っている者だ」と答えました。
山城の苅羽井は、当時、樺井月神社(かばいづきじんじゃ)があった綴喜郡樺井(つづきぐんかばい)、現在の京田辺市大住あたりだとされています。木津川の氾濫にともない、現在樺井月神社は、城陽市京田辺市大住水主(みずし)の水主神社の境内に鎮座しています。
 引用元:かむながらのみち ~天地悠久~
引用元:かむながらのみち ~天地悠久~志自牟の家に身を寄せる兄弟
その後お二人は河内の玖須婆(くすば)の川を渡り、さらに逃げて播磨の国へ入りました。

そこで志自牟(しじむ)という者の家に身を寄せ、素性を隠して牛飼い・馬飼いとして仕えていました。

河内の玖須婆の川は、大阪府枚方市楠葉(くずは)を流れる淀川だとされています。
播磨の国は、現在の兵庫県の南西部。
志自牟の家は、現在の兵庫県三木市志染町(しじみちょう)。
この頃、山部連小楯(やまべのむらじのおだて)が播磨の国守に任じられて赴任しました。

ある日、小楯は志自牟の新築祝いの宴に招かれ、賑わう席で人々は次々と舞を披露しました。
そのうち、竈のそばで火を焚いていた兄弟にも舞えと声がかかりました。
弟が「兄上からどうぞ」と譲れば、兄も「お前からやれ」と返す。人々は、賤しい火焚きの子らが互いに譲り合う姿を面白がり、大いに笑いました。

自分の身分を歌で明かす弟、袁祁王
そして兄が先に舞うと、次いで弟が、舞う前に朗々と歌いあげました。

「武人であるあなたが、太刀の柄に赤き飾りを施し、緒に赤い布をつけ、赤い旗を高く掲げれば、誰もが恐れて深く生い茂った竹藪の後ろに隠れてしまう。そんな竹薮の竹を裂き、その竹を並べて八弦の琴を作り、その調べを整えるように、履中天皇は天下を治められた。その皇子に市辺之忍歯王がおられた。我々は、その御子であるぞ。ここまで落ちぶれはしたが、ここに立つ二人は、履中天皇の孫で在り、正統な皇子なのだ」
 引用元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「履中天皇」
引用元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「履中天皇」
これを聞いた小楯は驚き、席から転げ落ちました。
すぐさま人々を追い出し、兄弟を膝の上に抱きとめて涙して、その労苦を労いました。そして人々を集めて仮宮を築かせ、兄弟をそこに迎え入れました。

後継者見つかる
ただちに小楯は早馬を立て、兄弟の叔母にあたる飯豊王(いいとよのみこ)に伝えました。

飯豊王はこの吉報を聞いて大いに喜び、二人の皇子をただちに宮中へお呼びになったのでした。

飯豊王は、履中天皇の皇女と市辺之忍歯王の王女、二つの説があります。前者なら兄弟の叔母、後者なら兄弟の姉ということになります。
飯豊王は、清貞天皇や飯豊天皇とし、天皇として扱われていることもあります。
古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)
清寧天皇
御子、白髮の大倭根子の命、伊波禮の甕栗の宮にましまして、天の下治らしめしき。
この天皇、皇后ましまさず、御子もましまさざりき。かれ御名代として、白髮部を定めたまひき。かれ天皇崩りまして後、天の下治らすべき御子ましまさず。ここに日繼知らしめさむ御子を問ひて、市の邊の忍齒別の王の妹、忍海の郎女、またの名は飯豐の王、葛城の忍海の高木の角刺の宮にましましき。
- 白髮の大倭根子の命(清寧天皇)
- 伊波禮の甕栗の宮(奈良県磯城郡)
- 葛城の忍海の高木の角刺の宮(奈良県南葛城郡)
市の邊の忍齒の王②王子たち
以下、市の邊の忍齒の王からの続き
ここに市の邊の王の王子たち、意祁の王、袁祁の王二柱。この亂を聞かして、逃げ去りましき。かれ山代の苅羽井に到りまして、御粮きこしめす時に、面黥ける老人來てその御粮を奪りき。ここにその二柱の王、「粮は惜まず。然れども汝は誰そ」とのりたまへば、答へて曰さく、「我は山代の豕甘なり」とまをしき。かれ玖須婆の河を逃れ渡りて、針間の國に至りまし、その國人名は志自牟が家に入りまして、身を隱して、馬甘牛甘に役はえたまひき。
- 意祁の王、袁祁の王(後の仁賢天皇と顯宗天皇)
- 山代の苅羽井(京都府相楽郡)
- 豕甘(豚を飼う者)
- 玖須婆の河(淀川)
- 針間の國(兵庫県の南部)
- 志自牟が家(兵庫県美嚢郡志染村(みなぎぐんしじみむら))
- 馬甘牛甘に役はえたまひき(馬や牛を飼う者として使われた。)
志自牟が新室楽
ここに山部の連小楯、針間の國の宰に任さされし時に、その國の人民名は志自牟が新室に到りて樂しき。ここに盛に樂げて酒酣なるに、次第をもちてみな儛ひき。かれ火燒の小子二人、竈の傍に居たる、その小子どもに儛はしむ。ここにその一人の小子、「汝兄まづ儛ひたまへ」といへば、その兄も、「汝弟まづ儛ひたまへ」といひき。かく相讓る時に、その會へる人ども、その讓れる状を咲ひき。ここに遂に兄儛ひ訖りて、次に弟儛はむとする時に、詠したまひつらく、
- 針間の國の宰(播磨の国の長官)
- 物の部(朝廷に仕える部族。古くは武士には限らない)
- 丹書き著け(大刀の柄に赤い絵を描き)
- 赤幡を裁ち(赤い織物を切って)
- 竹を掻き苅り、末押し靡かすなす(竹の末を押し伏せるように。勢いのよい形容)
- 八絃の琴を調べたるごと(絃の多い琴を弾くように。さかんにの形容)
- 伊耶本和氣の天皇(履中天皇)
- 奴、御末(われらはその子孫である)













