古事記現代語訳(51)雄略天皇②白い犬

雄略天皇の誕生
大長谷若建命(おおはつせのわかたけのみこと)、のちの第21代雄略天皇は、やがて大和の長谷(はつせ)の朝倉宮にお遷りになり、天下をお治めになりました。
 引用元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「雄略天皇」
引用元:『御歴代百廿一天皇御尊影』「雄略天皇」この御代には、大陸から大勢の呉人(くれびと)が渡来し、その人たちが住む土地を呉原(くれはら)と呼びました。

長谷の朝倉宮の場所は、奈良県桜井市黒崎または岩坂。または、同市の脇本遺跡も、朝倉宮の有力な候補地とされています。
 引用元:四国新聞社
引用元:四国新聞社呉人は、中国南北朝時代の南朝の人で、呉原は、現在は、栗原と呼ばれ、明日香村阿部山にある「キトラ古墳」の丘陵の東に位置しています。

雄略天皇は、亡き大日下王の同母妹にあたる若日下王を皇后とされました。

大日下王は、根臣という人物に騙された安康天皇によって暗殺されています。安康天皇は雄略天皇の同母兄です。
結納の品は白い犬
皇后がまだ河内の日下におられた時、雄略天皇は大和から近道の日下の直越(ただごえ)の峠を越えて、皇后のもとへとお向かいになりました。

河内の日下は、東大阪市日下町あたりです。
「日下の直越の峠」は、生駒山の暗峠(くらがりとうげ)を越える道だとされています。大和から直線的に越えるので直越といいます。河内と大和を最短で結ぶ古道です。「暗がり」の名称の起源は、樹木が鬱蒼と覆い繁り、昼間も暗い山越えの道であったからという説や「あまりに険しいので馬の鞍がひっくり返りそうになることから、鞍返り峠と言われるようになったという説があります。
その道中、天皇が生駒山の上から、四方の村々を見渡されますと、屋根の棟に鰹木を載せた一軒の家が目にとまりました。

鰹木は本来、天皇の宮殿か神社でなければ許されぬ格式の飾りなのです。
天皇はお供の者に尋ねられました。

「あの飾り木を載せた家は誰の家か?」
「志幾(しき)の大県主の家でございます」と答えが返ってきました。
これをお聞きになった天皇は、
「不遜なやつめ、自分の家をわが宮に似せて造っているな!」

とお怒りになり、家を焼き払えと命じられました。
大県主は恐れおののき、平伏して申しました。
「愚かにも分をわきまえず、過ってこのように造ってしまいました。どうかお許しください」と謝罪し、お詫びの印として一匹の白い犬を献上しました。

犬には布をまとわせ、鈴を飾り、腰佩(こしはき)という身内の者に縄を取らせて差し出したのです。
天皇はこれを受け入れ、家を焼き払うことをお許しになりました。
やがて皇后のもとに着くと、侍女に白犬を差し出して仰せになりました。

「これは今日の道中で得た珍しい生き物だ。結納の品として皇后に贈ろう」
しかし若日下王は、侍女を介して答えられました。
志幾は志紀郡のことで、志幾の大県主の家は大阪府藤井寺市惣社(そうしゃ)にあったとされています。志貴県主(しきあがたぬし)神社があります。
 引用元:藤井寺市
引用元:藤井寺市太陽を背にしてやってきたため若日下王に会えず
「本日あなたは太陽を背にしてお越しになりました。それは天照大御神に対して畏れ多いこと。そのため今日はお会いできません。改めて私の方からお仕えに参りましょう」

こうして天皇は一人お戻りの途中、山の坂に立ちとどまり、皇后への思いを歌に託されました。
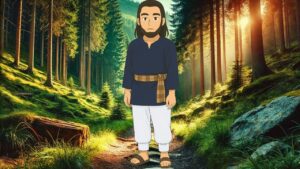
「日下部の山と、平群の山との谷間谷間に繁る樫の木よ。その根元には笹が茂り、枝先には竹が繁っている。あの竹のように、早く重なり合って添い寝をしたいものだ、愛しい妻よ」

この御歌を若日下王へお送りになり、その後まもなく皇后は朝倉宮へお上がりになりました。

日下部の山は、現在の生駒山で、平群の山は、現在の信貴山です。
古事記・読み下し文・注釈(武田祐吉・青空文庫より)
若日下部の王
大長谷の若建の命、長谷の朝倉の宮にましまして、天の下治らしめしき。
初め大后、日下にいましける時、日下の直越の道より、河内に出でましき。ここに山の上に登りまして、國内を見放けたまひしかば、堅魚を上げて舍屋を作れる家あり。天皇その家を問はしめたまひしく、「その堅魚を上げて作れる舍は、誰が家ぞ」と問ひたまひしかば、答へて曰さく、「志幾の大縣主が家なり」と白しき。ここに天皇詔りたまはく、「奴や、おのが家を、天皇の御舍に似せて造れり」とのりたまひて、すなはち人を遣して、その家を燒かしめたまふ時に、その大縣主、懼ぢ畏みて、稽首白さく、「奴にあれば、奴ながら覺らずて、過ち作れるが、いと畏きこと」とまをしき。かれ稽首の御幣物を獻る。白き犬に布を縶けて、鈴を著けて、おのが族、名は腰佩といふ人に、犬の繩を取らしめて獻上りき。かれその火著くることを止めたまひき。すなはちその若日下部の王の御許にいでまして、その犬を賜ひ入れて、詔らしめたまはく、「この物は、今日道に得つる奇しき物なり。かれ妻問の物」といひて、賜ひ入れき。ここに若日下部の王、天皇に奏さしめたまはく、「日に背きていでますこと、いと恐し。かれおのれ直にまゐ上りて仕へまつらむ」とまをさしめたまひき。ここを以ちて宮に還り上ります時に、その山の坂の上に行き立たして、歌よみしたまひしく、
疊薦 平群の山の、
此方此方の 山の峽に
立ち榮ゆる 葉廣熊白檮、
本には いくみ竹生ひ、
末へは たしみ竹生ひ、
いくみ竹 いくみは寢ずたしみ竹、
たしみ竹 たしには率宿ず、
後もくみ寢む その思妻、あはれ。 (歌謠番號九二)
- 日下(大阪府北河内郡生駒山の西麓)
- 日下の直越の道(生駒山のくらがり峠を越える道。大和から直線的に越えるので直越という)
- 堅魚を上げて舍屋を作れる家(屋根の上に堅魚のような形の木を載せて作つた家。大きな屋根の家。カツヲは、堅魚木の意。屋根の頂上に何本も横に載せて、葺草を押える材)
- 稽首の御幣物(敬意を表するための贈物)
- 妻問の物(妻を求むる贈物)
- 日下部の 此方の山(今立っている山、生駒山)
- 疊薦(枕詞)
- 平群の山(奈良県生駒郡の山)
- 此方此方の(あちこちの)
- いくみ竹(茂った竹)
- たしみ竹(しっかりした竹)
- いくみは寢ずたしみ竹(密接しては寝ず)
- たしには率宿ず(しかとは共に寝ず)













